 新人くん
新人くん「もう宅建の勉強、ムリかもしれない…。頑張っても全然覚えられないし、時間も取れない…」
宅建の勉強を続けていると、「やっても意味があるのかな」と感じる瞬間、ありますよね。
何度挑戦しても結果が出なかったり、仕事や家事との両立で限界を感じたり──。
そうなると、「自分には向いてないのかも」と思ってしまうのも無理ありません。
でも実は、**宅建をあきらめた人の中にも“その後に成功した人”がたくさんいます。**
一度離れたことで気持ちをリセットし、再挑戦して合格した人もいれば、
宅建の知識を別の形で活かしてキャリアを築いた人もいます。
この記事では、
– 宅建の勉強をあきらめたくなる理由
– 気持ちを切り替えるための行動
– もう一度挑戦したくなった人へのアドバイス
を、実体験とデータをもとにやさしく解説します。
「もうダメかも」と感じているあなたへ。
このページを読み終えた頃には、少しだけ前を向けるようになりますよ。
宅建の勉強をあきらめたくなる5つの理由
宅建の勉強をあきらめたくなる理由についてお話しします。
それでは、一つずつ見ていきましょう。
①頑張っても全然覚えられない
宅建の勉強をしていると、「昨日覚えたことをもう忘れてる…」ということ、ありませんか?
民法や宅建業法、法令上の制限など、出てくる言葉も内容もとにかくややこしい。暗記の量が膨大なので、どれだけ勉強しても頭に残らないと感じる人は本当に多いです。
これは決して「頭が悪い」わけじゃなく、宅建の勉強方法が合っていないだけなんですよね。テキストを読むだけだと定着しにくいので、過去問を中心に「問題を解きながら覚える」方法が効果的です。
ただ、それを知っていても、日々の疲れの中で机に向かうのは正直きついですよね。私も最初のころ、「なんでこんなにやってるのに頭に入らないんだろう…」と落ち込んでいました。
でもそれは、宅建を勉強する多くの人が通る“当たり前の壁”です。焦らず、自分のペースで進めていきましょうね。
②仕事や家事との両立がむずかしい
社会人や主婦の方にとって、宅建の勉強時間を確保するのは本当に大変です。
仕事でヘトヘトになって帰宅して、家のことを済ませたあとに勉強…。頭では「やらなきゃ」とわかっていても、体が動かないことってありますよね。
しかも、宅建は短期間でサクッと受かるような試験ではありません。合格するには、最低でも300時間以上の勉強時間が必要だと言われています。
だからこそ、「今日は疲れたからもういいや」と思ってしまうのも当然のこと。続かないのは意志が弱いからじゃなく、生活の中で無理をしているからなんです。
両立できないと感じたら、「一度距離を取る」選択もありですよ。ムリせずリズムを見直すことが、長い目で見ると一番の近道になります。
③やる気が続かない・集中できない
「最初はやる気満々だったのに、気づいたら勉強が苦痛になってきた…」という人も多いのではないでしょうか。
宅建の勉強は内容が地味で、達成感を感じにくいのが特徴です。努力がすぐに成果に結びつかないから、モチベーションが下がってしまうんですよね。
そんなときは、「勉強の目的」を見失っているサインです。なぜ宅建を取ろうと思ったのか、一度立ち止まって考えてみるといいです。
資格が欲しかった理由が明確になれば、やる気も少しずつ戻ってきますよ。小さな目標を立てて、「今日はここまでやれた!」と自分を褒めることも大切です。
完璧を目指さず、“続けられるペース”を意識していきましょう。
④何度も落ちて自信をなくした
「もう2回も落ちた…もう無理かもしれない」 そう感じるのは自然なことです。
宅建は国家資格の中でも合格率15〜17%程度と、決して簡単ではありません。しかも毎年、問題の傾向が変わるため、勉強しても「今年は難しかった」で終わることもあります。
ただ、ここで覚えておいてほしいのは、宅建試験に落ちる=才能がない ではないということです。
むしろ、何度も挑戦している時点で本当にすごい。諦めずに努力できる人こそ、最終的に結果を出すんです。
落ちたことを責めるよりも、「ここまで頑張れた自分」を認めてあげてくださいね。
⑤勉強しても意味がない気がしてきた
最後に多いのが、「もう意味がないんじゃないか」と感じる瞬間です。
頑張っても結果が出ないと、どうしても虚しくなりますよね。周りの人が合格していくのを見ると、「自分には向いてない」と思ってしまうのも無理はありません。
でも、それって今までの努力が“無駄”という意味ではないんです。宅建の勉強を通して得た知識や勉強習慣は、他の場面でも必ず活きます。
たとえば、FPや賃貸経営管理士など、宅建と親和性の高い資格を取るときも、その基礎が生きるんですよ。
「意味がない」と感じたときは、一度休む勇気を持ってください。時間を置けば、また見え方が変わることも多いです。
宅建を続けるのが難しい人に見られる5つの傾向
宅建の勉強を続けるのが難しい人には、共通する傾向があります。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
①目的があいまいなまま勉強している
宅建の勉強を続けられない人の多くは、「なぜ取るのか」が明確になっていないんです。
「とりあえず就職に役立ちそうだから」「みんなが取ってるから」といった理由で始めてしまうと、勉強がつらくなったときに支えがなくなります。
資格の勉強って、必ず“しんどい時期”がくるんですよ。そのとき、「どうして宅建を取ろうと思ったのか」という軸がないと、心が折れやすくなってしまいます。
逆に言えば、「この資格を取って将来こうなりたい」とイメージできる人ほど、最後まで走り切れるんですよね。
モチベーションを保つためには、“目的を言葉にして紙に書く”のもおすすめです。目に見える形にするだけで、心のブレが少なくなりますよ。
②「受かればいいや」と思ってしまっている
「まあ、受かればラッキーだよね」──こういう気持ちで勉強を続けている人は、途中で失速しがちです。
宅建試験は、運で受かる試験ではありません。基礎を理解して、何度も反復して、ようやく合格点に届くような構成なんです。
そのため、“なんとなく勉強している”状態だと、努力と結果がつながらずに苦しくなります。
とはいえ、「やる気が出ない」時期も誰にでもあります。そんなときは、最初から完璧を目指さず、「まずは10分だけ」でも机に向かうことが大切です。
行動すれば、少しずつ気持ちもついてきますからね。やる気は“出してから”ではなく、“やりながら出す”ものです。
③勉強時間をつくれない生活をしている
これは、社会人・主婦・子育て中の方にとても多い悩みです。
勉強時間を確保しようにも、仕事、家事、育児、付き合い…気づけば夜になっている。 「時間がない」は、宅建受験生の永遠のテーマですよね。
でも実は、「時間がない」というより、“勉強時間を確保できる仕組みをつくれていない”だけのことが多いんです。
例えば、朝30分だけ早く起きる、通勤時間にアプリで過去問を解く、昼休みに1問だけやる。こうした小さな習慣でも、積み重ねれば何十時間にもなります。
宅建は「短時間集中」でも合格できます。まとまった時間がなくても、コツコツ継続する人が勝つ試験です。
「完璧な勉強時間」を探すよりも、「今の生活の中でできる時間」を見つけることがポイントですよ。
④勉強そのものがつらくて苦痛
勉強を続けるうちに、「もう見るのもイヤ」「テキスト開くだけでしんどい」って感じること、ありませんか?
宅建は内容が法律中心で、正直おもしろいとは言いにくいですよね。しかも、解いてもすぐに結果が出ないから、モチベーションを保つのが大変です。
そんなときに大事なのは、“勉強の方法を変えること”です。
動画講座を使ってみる、音声で聞く、スマホアプリでクイズ感覚にする。方法を変えるだけで、気持ちが少し楽になることがあります。
「続けられない自分」を責めるのではなく、「続けられるやり方」を探すのが大事なんですよ。
勉強方法が合えば、自然とやる気も戻ってきますからね。
⑤他に本気でやりたいことがある
最後は、「本当は別のことをやりたい」と感じているケースです。
「宅建もいいけど、実は別の資格に興味がある」「今の仕事を続けるか迷っている」──そういう気持ちがあると、どうしても勉強に身が入りません。
それは決して悪いことじゃありません。むしろ、自分の本音に気づけた証拠です。
本当にやりたいことに気づいたなら、一度宅建から離れてみてもいいと思います。遠回りに見えても、最終的には“納得できる道”につながります。
大切なのは、「やめる」か「続ける」かではなく、自分の気持ちに正直に選ぶことです。 後悔のない選択をしていきましょう。
気持ちを切り替えて次に進むための行動5選
宅建の勉強をやめようと思ったあと、気持ちを切り替えて次に進むための行動を紹介します。
- ①不動産業界に未経験で挑戦してみる
- ②FPや賃貸経営管理士など別資格に挑戦する
- ③副業や在宅ワークで新しい道を探す
- ④宅建の勉強で得た知識を別の形で活かす
- ⑤一度離れて「またやりたい」と思えたら再挑戦する
宅建を手放したあとも、道はいくらでもあります。一つずつ見ていきましょう。
①不動産業界に未経験で挑戦してみる
「資格を取ってから働く」ではなく、「働きながら学ぶ」という選択もあります。
不動産業界は、宅建を持っていなくても採用されるケースが多いです。営業職・事務職・管理業務など、資格がなくてもできる仕事はたくさんあります。
実際に現場で働くことで、「この仕事、自分に合ってる」「思ったより面白い」と感じることもあります。逆に、「やっぱり違った」と気づけるのも大きな収穫です。
資格の勉強だけでは見えなかった“リアルな現場”を知ることが、自分のキャリアを見直すきっかけになりますよ。
もし興味があれば、「未経験OK 不動産」で求人を探してみるのもおすすめです。現場を知ることが、次のステップへの第一歩です。
②FPや賃貸経営管理士など別資格に挑戦する
宅建の勉強をした経験がある人は、他の資格にチャレンジすると驚くほどスムーズです。
特におすすめなのが、FP(ファイナンシャルプランナー)と賃貸経営管理士。どちらも宅建と重なる内容が多く、知識の再利用ができるんです。
| 資格名 | 学習範囲 | 活かせる宅建知識 |
|---|---|---|
| FP(ファイナンシャルプランナー) | 税金・不動産・保険・年金など | 不動産の売買や登記、権利関係 |
| 賃貸経営管理士 | 賃貸借契約・管理・トラブル対処など | 宅建業法や法令上の制限 |
特に賃貸経営管理士は、宅建よりも合格率が高く、不動産業界での評価も上がっている注目資格です。
「宅建は一旦お休み。でも学ぶことは続けたい」という人にはピッタリの選択肢ですよ。
③副業や在宅ワークで新しい道を探す
もし宅建の勉強をやめて時間に余裕ができたなら、その時間を“副業や新しい働き方”に使うのもおすすめです。
たとえば、Webライター、動画編集、ブログ運営、SNSマーケティングなど、今はスキルを活かして稼げる時代です。
しかも、宅建を勉強してきた人は「コツコツ努力できる力」がすでにあります。これって、副業でもものすごく活きるスキルなんですよ。
自分の興味をもとに、小さく始めてみましょう。最初は不安でも、やってみるうちに「あ、これ向いてるかも」と感じる瞬間がきっと来ます。
宅建を通して得た集中力や継続力は、どんな仕事にも通じる“武器”になります。
④宅建の勉強で得た知識を別の形で活かす
宅建の知識は、試験に合格しなくても役立つシーンがたくさんあります。
たとえば、自分が家を買うときや、賃貸契約をするとき。「重要事項説明」や「登記」などの言葉の意味がわかるだけで、かなり安心できますよね。
また、不動産投資やリフォームを考えるときにも、宅建の知識は実践的に使えます。自分の生活に“知識として還元”できるのは大きなメリットです。
「資格を取らなかった=意味がなかった」ではなく、「学んだことを別の形で使う」という発想を持つと、気持ちが軽くなりますよ。
⑤一度離れて「またやりたい」と思えたら再挑戦する
いったん宅建の勉強から離れると、ふとした瞬間に「もう一回やってみようかな」と思うことがあります。
それは、心が少し休んで元気を取り戻した証拠です。焦らずに離れたからこそ、本当の気持ちに気づけるんですよね。
再挑戦を決めたときは、以前と同じやり方ではなく、勉強法を見直すことが大事です。通信講座を使う、勉強仲間を作る、スキマ時間を活用するなど、負担の少ないやり方を選びましょう。
「あのときは無理だったけど、今ならできるかも」──そう思えたなら、それはもう立派なスタートです。
あきらめた経験がある人ほど、次の挑戦では強くなれます。焦らず、一歩ずつ前へ進みましょう。
もう一度宅建に挑戦したい人へ伝えたい6つのこと
もう一度宅建に挑戦したい――そう思えたあなたに、ぜひ伝えたいことがあります。
この6つを意識するだけで、次の挑戦はまったく違うものになります。
①過去の失敗を「経験」として活かそう
まず伝えたいのは、「失敗は失敗じゃない」ということです。
一度うまくいかなかったのは、ただ「合格までの道を確認できた」だけ。 何がダメだったのか、どこでつまずいたのかを振り返ることが、次の成功への一番の近道です。
例えば、苦手分野が「民法」だったのか、「時間配分」だったのか。原因を明確にすることで、次の勉強法が変わります。
過去の自分を責める必要なんてありません。むしろ、諦めずに「また挑戦しよう」と思えるあなたは本当に強いんです。
一度の失敗を、成功への“リハーサル”だと考えてみてくださいね。
②効率的な勉強法に切り替える
宅建は、やみくもに時間をかけても合格できる試験ではありません。
大切なのは、“効率”です。たとえば、過去問を中心に学ぶこと。宅建試験は毎年似たような出題傾向があり、過去問の理解度が合否を左右します。
また、「テキスト→問題→解説→復習」という流れを繰り返すよりも、「問題→解説→理解」で先に実践的に触れるほうが頭に残りやすいです。
時間が限られている社会人ほど、「勉強量より質」を意識してくださいね。
スマホアプリや音声学習など、今は手軽に使えるツールも増えています。自分に合った勉強スタイルを見つけることが、再挑戦のカギです。
③通信講座を使ってみる
独学で挫折した経験がある人は、通信講座を活用するのもおすすめです。
通信講座のいいところは、「勉強のペース管理を任せられる」ことと、「理解しづらい部分をプロが解説してくれる」こと。
とくに、動画講座形式のものなら、通勤時間やスキマ時間にも勉強できます。 「時間がないから無理」という言い訳を減らせるんですよ。
もちろん、教材の質も重要ですが、一番大切なのは“続けられる仕組み”があること。 毎日の学習リズムをサポートしてくれる講座を選べば、無理なく継続できます。
たとえばスタディングやアガルートなど、宅建に特化した通信講座は、短期間で合格した受験生からの支持も高いです。 一人で頑張るより、上手に「仕組み」を使うのも戦略ですよ。
④一人で抱えず勉強仲間を見つける
人は一人だと、どうしても弱気になります。でも仲間がいるだけで、気持ちは全然違うんです。
たとえばSNSやX(旧Twitter)では、宅建受験アカウントがたくさんあります。 「今日は過去問3年分終わった!」みたいな投稿を見るだけでも刺激になりますよ。
同じ目標を持つ人がいると、「自分も頑張ろう」と自然に思えるんです。
勉強仲間を見つけることで、孤独感が減って、継続力も上がります。 一緒に励まし合える人を見つけてみてくださいね。
⑤自分のペースでコツコツ進める
再挑戦で一番大切なのは、「無理をしないこと」です。
前回の失敗を取り戻そうと、最初から飛ばしてしまう人もいますが、それだとまた疲れてしまいます。
合格は“速さ”ではなく“継続力”で決まります。 1日10分でもいい。5問だけでもいい。小さな積み重ねを続けることが、いちばんの近道なんです。
周りと比べず、昨日の自分に勝つ気持ちでいきましょう。 少しずつ、確実に進めていけば大丈夫です。
⑥合格した先の未来を思い描く
最後に、これが一番大切です。 「合格したらどんな未来が待っているか」をイメージすること。
たとえば、「資格を取って不動産会社で働きたい」「独立して自分の事務所を持ちたい」「家族を安心させたい」。 その未来をリアルに描くことで、勉強が“やらなきゃ”から“やりたい”に変わります。
宅建は、努力が結果に直結する資格です。 あなたが本気で目指せば、必ず届きます。
そして、あきらめた経験がある人ほど、もう一度立ち上がったときの強さは本物です。
焦らず、自分のペースで。 次は、きっと合格をつかめますよ。
まとめ|宅建をあきらめたあとにできる前向きな選択
| 内容 | リンク |
|---|---|
| 勉強がつらくなる理由を知る | 宅建の勉強をあきらめたくなる5つの理由 |
| 続けるのが難しい人の傾向を理解する | 宅建を続けるのが難しい人に見られる5つの傾向 |
| 前を向くための行動を見つける | 気持ちを切り替えて次に進むための行動5選 |
| 再挑戦のためのヒントを得る | もう一度宅建に挑戦したい人へ伝えたい6つのこと |
宅建の勉強は本当に大変です。 だからこそ、「あきらめた」と感じた瞬間も、決して無駄な時間ではありません。
あのとき感じた苦しさや挫折も、必ずあなたの中に“経験”として残っています。 そしてその経験が、次に何かを選ぶときの強さになります。
もし今、「もう少しだけ頑張ってみようかな」と思えたら、 通信講座を使ってみたり、SNSで勉強仲間を見つけたりするのも一つの手です。
逆に、「やっぱり違う道に進もう」と感じたなら、それも立派な前進です。 あきらめることは、逃げることではなく、“選び直す勇気”なんですよ。
宅建を通して得た知識と努力は、きっとどんな道にも生きていきます。 焦らず、自分らしいペースで歩んでいきましょう。
参考リンク:国土交通省:宅地建物取引士に関する情報




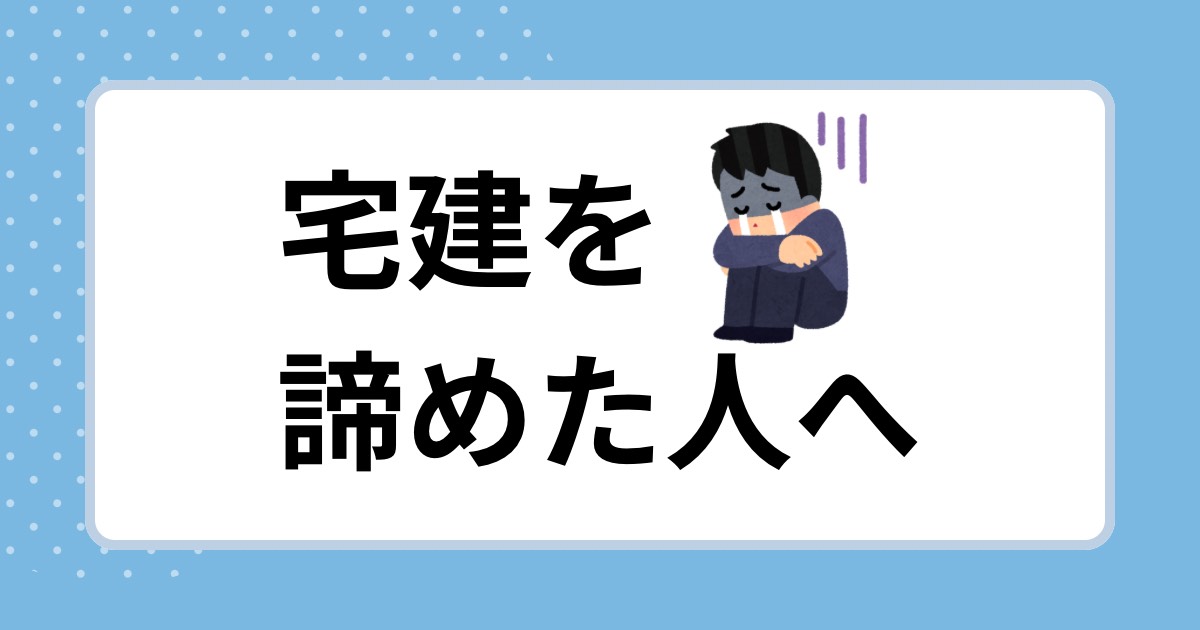
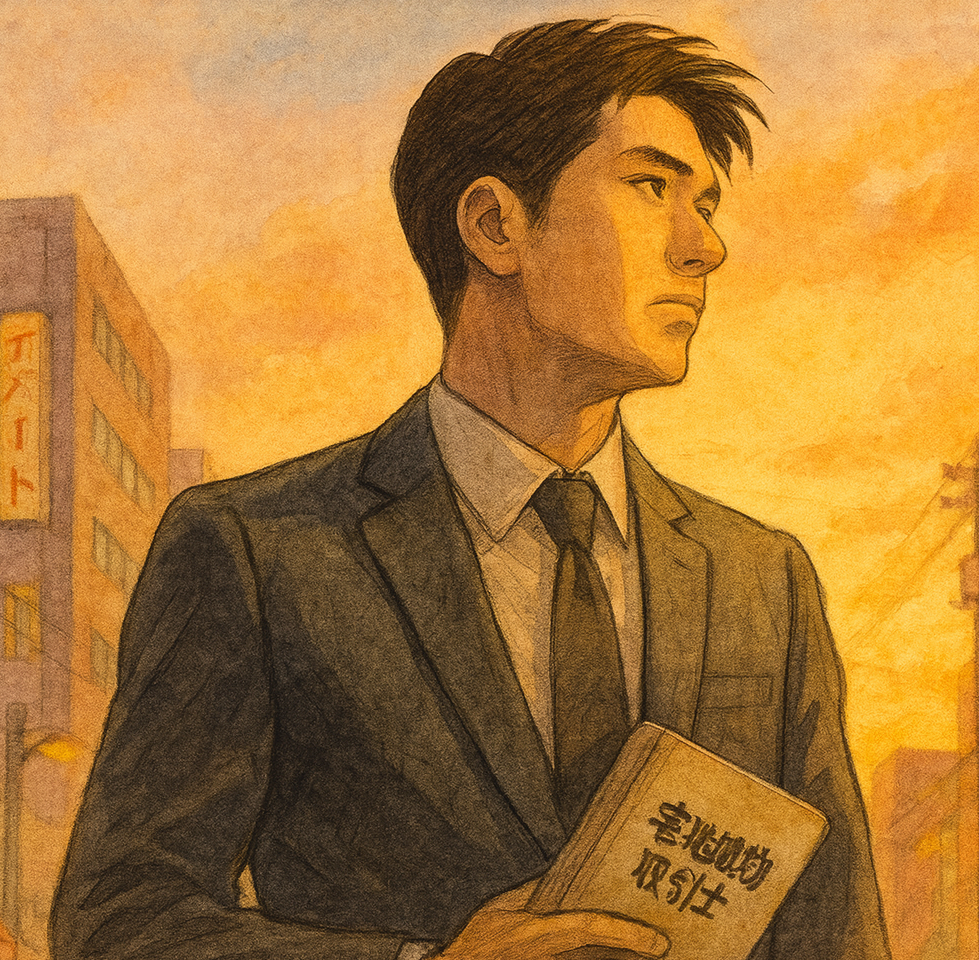
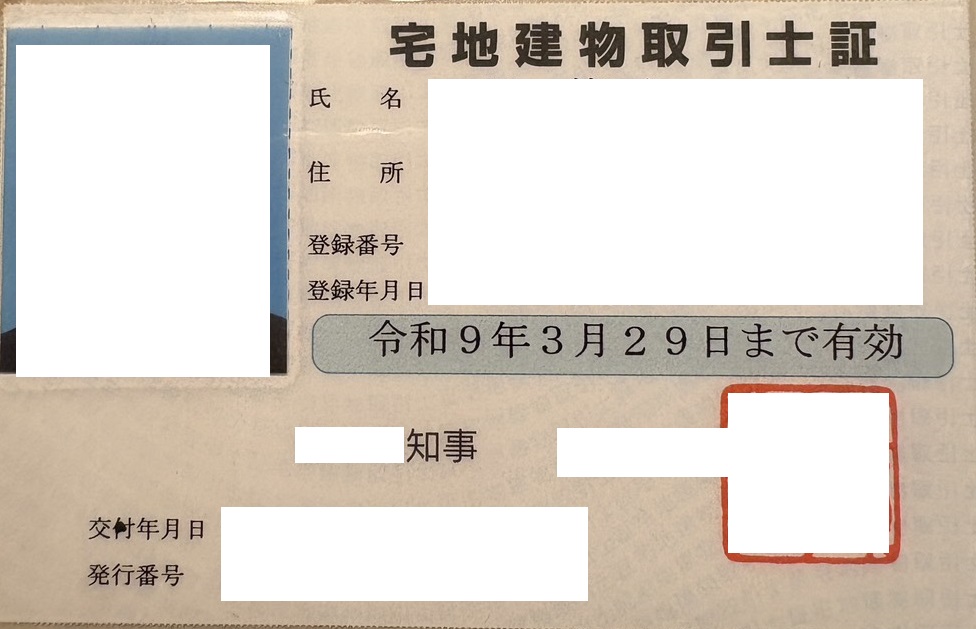







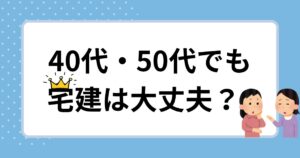

コメント