 新人くん
新人くん宅建の勉強方法って、独学・通信講座・通学講座のどれを選べばいいですか?
宅建は国家資格の中でも人気が高く、勉強スタイルによって合格までの道のりが大きく変わります。
この記事では現役の不動産営業マンが、自分の体験談を交えつつ、それぞれの勉強法のメリット・デメリットを分かりやすく比較して解説します。
未経験の人が安心して学べる方法や、業界経験者が効率よく勉強を進めるポイントも紹介しています。
最後まで読めば「自分に合った宅建の勉強方法」が見つかるはずです。
宅建勉強方法の基本を徹底解説
宅建勉強方法の基本を徹底解説します。



宅建の勉強を始めたいんですけど、まずどんな選択肢があるんですか?独学とか通信とか、何が違うのか分からなくて…。



いい質問だね。宅建は「独学」「通信講座」「通学講座」の3つが基本の勉強方法なんだ。どれを選ぶかで勉強の進め方も、合格までの道のりも大きく変わってくるよ。
①合格に必要な勉強時間の目安
宅建合格に必要な勉強時間は300〜400時間前後といわれています。これはあくまで目安で、業界経験や学習効率によって変わります。
例えば法律知識がゼロの未経験者なら400時間以上を見込んだ方が安心ですし、逆に不動産業界で働いていて用語に慣れている人なら250時間程度でも合格ラインに届くケースがあります。
出典:国土交通省 宅建試験実施状況(最終確認日:2025年9月)
②宅建試験の出題範囲と特徴
宅建試験は「権利関係」「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」の4分野から50問が出題されます。マークシート4択形式で、合格点は毎年35点前後です。
特に宅建業法は20問と配点が大きく、得点源にしやすい分野です。逆に「税・その他」は出題数が少ないため、勉強の優先度を下げる人も多いです。
効率よく点数を積み重ねるために、得点源と割り切る分野を見極めるのがカギになります。
③独学・通信講座・通学講座の比較ポイント
宅建の勉強方法には大きく3つあります。
- 独学:コストを抑えて自分のペースで勉強できる
- 通信講座:効率的に学べて質問サポートもある
- 通学講座:直接質問できるが、時間と費用がかかる
どれを選ぶかは、自分の環境や性格によって変わります。不動産業界にいて周囲に質問できる環境がある人は独学でも合格可能ですが、未経験者には通信講座の方が安心です。
このあと、それぞれの方法を詳しく解説しますね。


宅建を独学で勉強する方法と特徴
宅建を独学で勉強する方法と特徴を解説します。
①独学のメリット
独学の一番のメリットは、コストを大幅に抑えられることです。市販のテキストと過去問集を用意すれば1〜2万円程度で学習を始められます。
また、自分のペースで勉強できるため、得意な分野に時間をかけず、苦手分野を重点的に学習できるのも独学の強みです。
スキマ時間に柔軟に取り組めるため、忙しい社会人にとっては効率的な方法にもなります。
②独学のデメリット
一方で独学のデメリットは「質問できないこと」と「モチベーションが続きにくいこと」です。
宅建は法律用語や業界特有の知識が多いため、初学者は理解に時間がかかります。疑問点が解決できないまま進むと、効率が落ちてしまいます。
また、学習計画や進捗管理もすべて自分次第なので、途中で挫折する人も少なくありません。
③独学に向いている人(業界経験者向き)
独学が向いているのは、不動産業界で働いている人や、周囲に宅建合格者がいる人です。分からないことを職場で質問できる環境があれば、独学でも十分に合格可能です。
私自身も、不動産賃貸営業をしながら独学を中心に勉強しました。業界用語は日常的に耳にしていたので、法律知識がゼロの未経験者よりも学習を進めやすかったと思います。
ただし未経験者の場合は、独学だと壁にぶつかりやすいため通信講座を検討するのがおすすめです。
④独学で合格する具体的な勉強法
独学で合格するための基本は「テキスト+過去問」の徹底反復です。特に過去問は10年分を最低3周、できれば5周以上繰り返すと合格に近づきます。
テキストは複数に手を出さず、1冊を使い込むことが重要です。私は「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」と過去問集を軸に勉強しました。
また、スキマ時間にはYouTube(ゆーき大学)やアプリを使い、理解が弱い部分を補強しました。電車移動中や休憩中でも知識を積み上げられるのは独学の強みです。
独学は大変ですが、環境次第では十分に合格できる方法です。
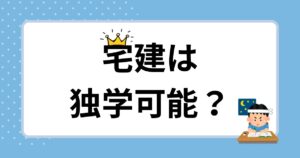
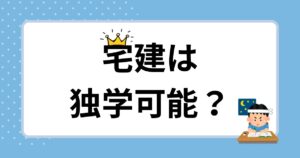
宅建を通信講座で勉強する方法と特徴
宅建を通信講座で勉強する方法と特徴を解説します。
①通信講座のメリット
通信講座の最大のメリットは、効率的なカリキュラムとサポートが揃っている点です。講師による動画解説や図解付き教材があるため、初学者でも理解しやすくなっています。
また、質問サポートや添削課題がある講座を選べば、疑問点をそのままにせず学習を進められます。独学でつまずきやすい部分を補えるのが強みです。
さらに、通学講座よりも費用が抑えられるため、コストパフォーマンスにも優れています。
②通信講座のデメリット
一方で通信講座は、自己管理が必要です。学習スケジュールは自分で守らなければならないため、途中で挫折してしまう人もいます。
また、サポート体制は講座ごとに差があります。質問対応のレスポンスが遅い講座だと、不満が残るケースもあるので、選ぶ際には注意が必要です。
③通信講座に向いている人(未経験者におすすめ)
通信講座は、特に不動産業界未経験者におすすめです。法律用語や業界知識に不安がある人でも、質問ができる環境があれば安心して勉強を進められます。
私の前職の上司も未経験で宅建を受験しましたが、通信講座を利用して効率よく学習し、合格していました。未経験者が独学だけで合格を目指すのはハードルが高いため、通信講座が現実的な選択肢になります。
④通信講座で合格する具体的な勉強法
通信講座を活用する場合は、講座のカリキュラムに沿って進めるのが基本です。動画でインプットを行い、問題集や過去問でアウトプットする流れを繰り返します。
添削課題や小テストを活用し、理解度をチェックしながら進めることで効率的に合格力を高められます。
また、質問サポートを積極的に利用することも重要です。分からないところを放置せず、その都度解決して進めることで合格に近づけます。
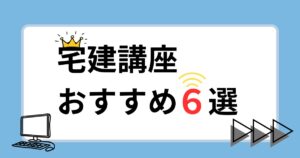
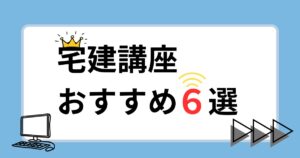
宅建を通学講座で勉強する方法と特徴
宅建を通学講座で勉強する方法と特徴を解説します。
①通学講座のメリット
通学講座のメリットは、決まった時間に教室へ行くことで「勉強せざるを得ない環境」が作れることです。独学ではついサボってしまう人にとって、強制力が働くのは大きな利点です。
また、講師に直接質問できる点や、同じ試験を目指す仲間と一緒に勉強できる点もモチベーション維持につながります。
②通学講座のデメリット
ただし通学講座には、費用が高額(10〜20万円前後)になることや、通学時間が必要になるというデメリットがあります。
さらに最近は授業の多くが動画視聴形式になっているケースもあり、「通わなくても良いのでは」と感じる人も少なくありません。
③通学講座に向いている人
通学講座は「一人では勉強を続けられない人」や「直接講師に質問したい人」に向いています。
また、勉強仲間が欲しい人や、環境に強制されないと勉強に取り組めない人には有効な方法です。
一方で、忙しい社会人や効率を重視したい人には通信講座や独学の方が合っている場合も多いです。
④実際に通ってみた体験談(4回しか行かなかった理由)
私自身も通学講座に申し込んだ経験がありますが、実際に通ったのは4回だけでした。
理由は、授業の多くが動画視聴形式だったことです。正直「これなら自宅でできる」と思ってしまい、足が遠のきました。
さらに、営業の仕事をしながら通うのは時間的にも厳しく、最終的には独学中心で勉強を進めました。
通学講座が悪いわけではありませんが、私には効率が合わなかったというのが正直な感想です。
働きながら宅建に合格する勉強のコツ
働きながら宅建に合格する勉強のコツを紹介します。



仕事をしながら宅建の勉強って本当にできますか?毎日残業もあるし、まとまった時間が取れる気がしないんです…。



その不安はよく分かるよ。俺も営業の仕事をしながらだったから、時間は全然足りなかった。でも工夫次第で十分合格できるんだ。大事なのは「短い時間でも継続」することと、環境を整えることだよ。
①毎日のルーティンに組み込む
勉強を「生活の一部」にしてしまうのが一番の近道です。例えば通勤電車の中で過去問を解く、朝起きたらテキストを1ページ読む、寝る前にアプリでクイズをするなど、日常に組み込むのがコツです。
私も毎日決まった時間に勉強する習慣を作ることで、少しずつ勉強時間を積み重ねていきました。
②短時間でも継続を優先する
宅建の勉強は「1日3時間やらなきゃ」と気負うより、「10分でも続ける」ことが大切です。短い時間でも毎日積み重ねる方が記憶に残りやすく、モチベーションも維持しやすいです。
忙しい日こそ「今日は10分だけ」と割り切ることが、長期的な合格につながります。
③動画やアプリを活用する
スマホアプリやYouTubeの講義動画は、スキマ時間の強い味方です。特に移動中や待ち時間に動画でインプットするのは効率的でした。
私も「ゆーき大学」のYouTube講義をよく使っていて、分かりにくい法律用語の理解に役立ちました。
④職場や家族の理解を得る
働きながら合格を目指すなら、周囲の理解も大切です。私は職場の上司に「宅建を必ず取る」と宣言していたので、勉強の時間を少し工夫できました。
家族や同僚に理解してもらうことで、勉強に集中しやすい環境を作れます。特に職場で宅建を応援されると、合格後の評価にもつながります。
宅建合格者の体験談から学ぶ勉強法の選び方
宅建合格者の体験談から学ぶ勉強法の選び方を紹介します。



結局どんな勉強法で合格したんですか?僕も自分に合う方法を選びたいんですけど…。



タク: 俺の場合は、不動産業界で働いていたから先輩に質問できたし、業界用語も1年目である程度理解できていた。だから通学講座は4回しか行かず、実質ほぼ独学で勉強したんだ。でも、未経験の人なら通信講座を使う方が効率的だと思うよ。自分に合う方法を選んでほしい。
①初回不合格からのリベンジ
私は初回の受験で23点しか取れず、不合格でした。正直かなりショックでしたが、この経験が「次は絶対に受かる」と本気になれたきっかけです。
失敗を経て、勉強の方法や時間配分を大きく見直すようになりました。
②独学+過去問を中心にした実体験
私が使ったのは市販のテキストと過去問集(LECの過去問)です。テキストは『みんなが欲しかった!宅建士の教科書』を使い、徹底的に読み込みました。
過去問は繰り返し解くことで出題パターンに慣れ、点数を安定させることができました。結局これが合格の決め手になったと思います。
③9月から追い込みで合格した方法
勉強を本格的に始めたのは試験の2か月前でした。それまでは仕事が忙しく、あまり手をつけられていなかったんです。
9月からは毎日2〜3時間を勉強にあて、休日は5時間以上やるようにしました。短期間で集中して追い込みをかけたことで、合格点に到達できました。
④経験者と未経験者で勉強法をどう選ぶか
私のように不動産業界にいて質問できる環境がある人なら、独学でも十分合格できます。
一方で未経験者は、専門用語や法律知識でつまずくことが多いので、質問できる通信講座を利用するのが現実的です。
大事なのは「自分の環境に合った勉強方法を選ぶ」こと。独学・通信・通学の3つを比較して、自分にとって最も続けやすい方法を選んでください。
まとめ|宅建勉強方法は自分に合うスタイルを選ぶことが大切
宅建の勉強方法は「独学・通信講座・通学講座」の3つがあり、それぞれに特徴があります。
私自身はほぼ独学で合格しましたが、未経験者にとっては通信講座の方が安心できる場面が多いはずです。
大事なのは「環境や性格に合った方法を選ぶこと」。そうすれば働きながらでも合格は十分可能です。
宅建は合格すればキャリアにも直結する資格なので、早めに準備を始めるのがおすすめですよ。






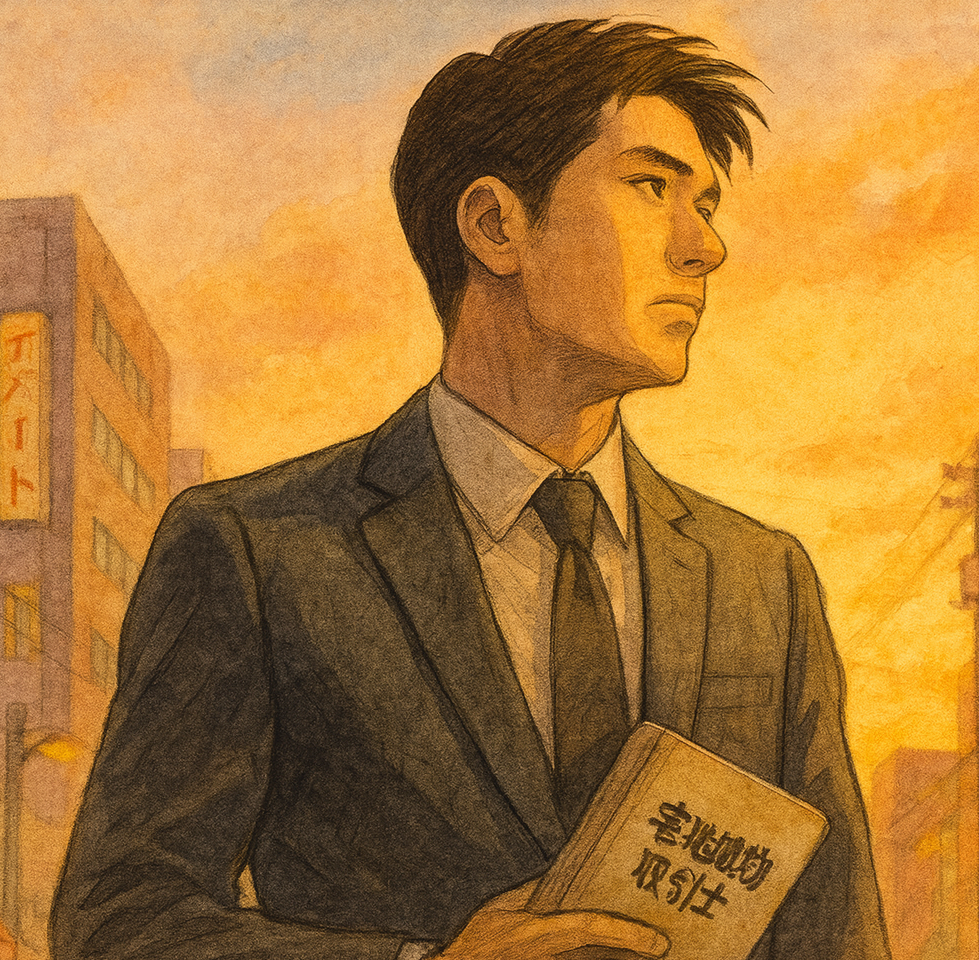
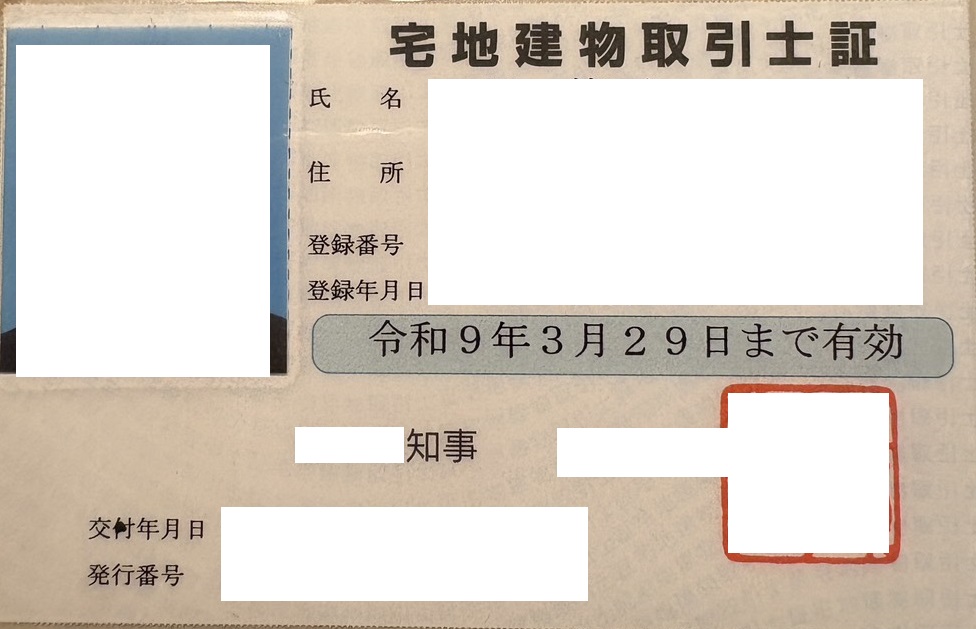








コメント