 新人くん
新人くん「宅建の勉強って、どのくらいの期間で合格できるんだろう?今から始めても間に合うのかな…」
宅建の勉強を始めようと思っても、「どれくらい時間が必要なのか」「何をどの順番でやればいいのか」って迷いますよね。
SNSやネットでは「半年あれば余裕」「3か月でも受かる」「1か月で一発合格も可能」なんて声もあって、正直どれを信じていいか分からない人も多いはず。
結論から言うと、**宅建は勉強期間よりも“やり方”がすべてです。**
正しい戦略で進めれば、受かる可能性は十分あります。
この記事では、
– 宅建に合格するために必要な勉強時間の目安
– 残り期間別(6か月・3か月・1か月)のスケジュール例
– 忙しい社会人・主婦でも合格できる勉強法
を、実際の合格者データとリアルな体験をもとに解説します。
「今からでも受かる方法を知りたい」
「自分のペースで効率よく勉強を進めたい」
そんな方に向けて、**最短で合格をつかむための“現実的なロードマップ”**をお伝えします。
残り期間別で見る!宅建に必要な勉強時間と1日の学習量
宅建に必要な勉強時間と、残り期間ごとの1日あたりの学習量をまとめました。
それでは順番に見ていきましょう。
①6か月・4か月・3か月・2か月・1か月の必要勉強時間まとめ表
まずはこちらの表をご覧ください。宅建試験(10月中旬)から逆算した、残り期間別の勉強時間と1日あたりの目安です。
| 残り期間 | スタート 時期目安 | 初学者の 必要勉強時間 | 既修者・業界経験者の必要勉強時間 | 初学者の1日あたり勉強時間 | 既修者の1日あたり勉強時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月前 | 4月中旬 | 約350時間 | 約250時間 | 約2時間 | 約1.5時間 |
| 4か月前 | 6月中旬 | 約350時間 | 約250時間 | 約3時間 | 約2時間 |
| 3か月前 | 7月中旬 | 約350時間 | 約250時間 | 約4時間 | 約2.5時間 |
| 2か月前 | 8月中旬 | 約350時間 | 約250時間 | 約6時間 | 約3.5時間 |
| 1か月前 | 9月中旬 | 約350時間 | 約250時間 | 約12時間 | 約8時間 |
初学者の場合、合格には最低でも300〜350時間の学習が必要です。既修者・業界経験者は知識の土台がある分、約250時間を目安にすると良いですね。
つまり「6か月前=4月中旬」から始めれば、毎日2時間で十分間に合います。一方で「8月中旬(2か月前)」スタートなら、毎日6時間は必要なペースになります。
②今から間に合わせるための逆算スケジュール
宅建勉強のスケジュールは、「いつから始めるか」よりも「試験日までに何を終わらせるか」を決めるのが大切です。
理想的なペース配分は次の通りです。
| 期間 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 前半(全体の40%) | テキストを1周+全範囲の概要把握 | 理解は浅くてOK。「こういうことを学ぶんだ」で十分。 |
| 中盤(全体の40%) | 過去問演習+YouTubeで理解を深める | 問題を解きながらテキストに戻る流れが最強。 |
| 後半(残り20%) | 模試・苦手分野の潰し込み | 「わからない問題」より「確実に取れる問題」を増やす。 |
宅建は「勉強時間の多さ」よりも「時間配分」が勝負です。どんなに短期間でも、毎日の積み重ねが合否を分けます。
③全くの初心者が間に合わせる勉強法
もしあなたが宅建初挑戦なら、最初に完璧を目指さないことが鉄則です。いきなり理解しようとせず、全体を俯瞰するのがコツです。
おすすめの流れは次の通りです。
- テキストをざっと読む(理解は浅くてOK)
- YouTubeで好きな講師の解説を視聴
- 動画で扱われたテーマの問題集を解く
- 間違えた問題の解説をテキストで読む
このサイクルを1〜2日単位で回すことで、短期間でも「問題に慣れる→知識が定着する→点が取れる」の循環を作れます。
特に、テキストを最初から丁寧に読み込もうとすると時間を無駄にしてしまうので、まずは「こんな内容なんだ」と流し読みでOKです。問題を解いてから戻るほうが理解が深まりますよ。
④短期間合格者に共通する学習習慣
短期合格者の多くに共通するのは、「勉強時間を固定する習慣」です。朝型でも夜型でも構いませんが、毎日同じ時間帯に机に向かうリズムをつくると集中力が上がります。
また、「1日〇時間やる」ではなく、「この時間帯に勉強する」と決めるのがポイントです。人間の集中力は“ルーティン化”することで最大化します。
さらに、1日1回は必ず過去問を解く習慣をつけておくと、出題傾向が肌感で掴めるようになります。宅建は過去問ゲーと言われるほど、出題形式が似ている試験です。
自分のペースを崩さず、毎日少しずつ積み上げていけば、2か月前スタートでも十分合格圏内に届きますよ。
宅建 勉強期間を短縮する効率的な勉強法
宅建 勉強期間を短縮する効率的な勉強法について解説します。
短期間で宅建に合格したいなら、「正しい勉強の順番」を意識することが何より大切です。
①インプット3割・アウトプット7割の法則
宅建勉強でありがちな失敗は、「テキストを何周も読むことに時間を使ってしまう」ことです。
実は、理解するより「解く」ことの方がずっと重要です。宅建の試験は知識を暗記する試験ではなく、「知識を使って判断する」試験だからです。
そのため、理想的な学習配分は、インプット3割・アウトプット7割。テキストで学ぶより、問題を解きながら知識を定着させていく方が圧倒的に効率がいいです。
例えば、1時間勉強するなら、20分テキスト→40分問題演習。このバランスを保つだけで、理解の深さとスピードが両立します。
「覚えるために読む」のではなく、「解くために読む」。これが短期合格の最大のコツです。
②最短で伸びる勉強サイクル(テキスト→動画→問題→復習)
筆者が実際にやって一番効果が高かったのが、この勉強サイクルです。
- まずテキストをざっと読む(理解は浅くてOK)
- YouTubeなどで好きな講師の解説を視聴する
- 動画で扱われたテーマの問題集を解く
- 間違えた箇所だけ、テキストの解説を読む
この順番で学習すると、頭に「全体像→理解→実践→確認」という流れが自然にでき、短時間で知識が定着します。
テキストを最初から理解しようと頑張るより、「とりあえず触れてみる」ぐらいの気持ちがベストです。最初は理解しきれなくても、YouTubeの解説や問題演習を通して、次第に“線がつながってくる”感覚になります。
特に独学者の場合、YouTubeを使うと“先生が横で教えてくれてる感”があるので、孤独感がなくなって勉強が続きやすいです。宅建みやざき塾やアガルートなど、無料で質の高い講義が多いのも魅力です。
問題集を解いた後にテキストで確認する流れを繰り返すと、覚えにくかった法律用語や条文も自然に頭に残るようになります。
「理解してから解く」より、「解いてから理解する」。これが短期合格の思考法です。
③過去問・模試・アプリの使い分け方
宅建試験は「過去問ゲー」と言われるほど、出題傾向が毎年似ています。ですから、過去問の繰り返し演習が最も効率的な勉強法です。
具体的には次のように使い分けましょう。
| 教材 | 使い方 | 目的 |
|---|---|---|
| 過去問集 | 最低でも3年分を3周 | 出題パターンと頻出論点の把握 |
| 模試 | 試験1か月前に2〜3回受験 | 時間配分と本番の集中力を鍛える |
| スマホアプリ | 通勤・通学のスキマ時間に復習 | 知識の穴を埋める+定着の確認 |
ポイントは「同じ問題を何度も解く」こと。1回で解けなくても構いません。2回、3回と繰り返すうちに、“この問題見たことある”という状態になれば合格圏内です。
スマホアプリを使えば、仕事や家事の合間に5分単位で勉強できるので、特に社会人にはおすすめですよ。
④勉強を継続するためのモチベ維持術
短期間で結果を出すには、「継続」がすべてです。どんなに効率的な方法でも、続かなければ意味がありません。
筆者がやって効果的だったのは、「小さな達成感を毎日つくる」ことです。例えば、「今日は10問だけ」「今日はテキスト1ページだけ」といったミニ目標を設定します。
また、勉強時間を記録するのもおすすめです。1日2時間でも、1週間で14時間、1か月で60時間以上。目に見える数字が積み上がると、自信に変わります。
どうしてもやる気が出ない日は、宅建YouTuberの合格体験談を見たり、SNSで同じ受験生をフォローすると刺激をもらえます。
勉強を「我慢」ではなく「習慣」に変えた人が、最終的に合格をつかみますよ。
時間がなくても諦めない!社会人・主婦でも合格できる学習戦略
時間がなくても諦めない!社会人・主婦でも合格できる学習戦略を紹介します。
宅建は社会人・主婦でも合格率が高い資格です。ただし「限られた時間でどう効率的に進めるか」が合否の分かれ目です。
①タイムマネジメントと優先順位の付け方
時間がない人ほど、まずやるべきは「時間を増やすこと」ではなく、「時間の使い方を変えること」です。
1日の中で“無意識にスマホを触っている時間”“なんとなくテレビを見ている時間”を15〜30分減らすだけで、勉強時間は作れます。
例えば、朝30分早起きする、昼休みにYouTubeで宅建講義を観る、夜寝る前に過去問を1問解く。これをルーティン化すれば、1日2時間程度は確保できます。
また、勉強の優先順位を明確にするのも重要です。完璧に覚えようとせず、「出るところだけ集中する」。これが短期合格者の共通点です。
②家事・仕事・勉強を両立するスケジュール術
社会人・主婦の場合、勉強時間は「隙間時間をどう使うか」で決まります。
スケジュールを立てるときは、「固定時間+隙間時間」で組み立てると現実的です。
| 時間帯 | 行動例 | 勉強内容 |
|---|---|---|
| 朝(出勤前・家事前) | 30分早起きしてテキストを流し読み | 民法・宅建業法の基礎理解 |
| 昼休み・通勤中 | スマホでYouTube講義やアプリ演習 | 重要ポイントの確認 |
| 夜(家事・仕事後) | 1時間だけ過去問演習+復習 | アウトプット中心の勉強 |
このように、1日2時間の“積み上げ型スケジュール”を習慣化すれば、6か月前からであれば十分に合格圏内です。
特に「夜疲れて集中できない人」は、朝に勉強時間をずらすとパフォーマンスが上がります。1日1回、同じ時間帯に机に向かうことが大事ですよ。
③家族の理解を得ながら学習を続けるコツ
家庭がある人の場合、勉強を続ける最大の壁は“家族の理解”です。
「ママ(パパ)は今、資格の勉強をしてるんだ」と事前に伝えておくと、家族の協力が得やすくなります。
また、「勉強する時間」を共有スケジュールに書き込むのもおすすめです。見える化すると、家族も自然とサポートしてくれるようになります。
小さいお子さんがいる場合は、子どもが寝た後に集中して勉強する“深夜型”も効果的です。夜1時間でも、毎日続けることが大切です。
家族と一緒に「資格合格」という目標を共有できると、モチベーションも維持しやすくなります。
④直前期の追い込み勉強法(残り1か月)
試験まで残り1か月を切ったら、勉強法を「量」から「質」に切り替えましょう。
この時期は新しい知識を入れるより、「今ある知識を確実に点にする」フェーズです。
- 苦手分野を付箋でリストアップ
- 過去問をもう一度解き直す
- 模試で時間配分の確認
特に宅建業法と権利関係(民法)は配点が高いため、ここを重点的に復習するのが効率的です。
「全範囲を完璧に覚える」ではなく、「自分が解ける問題を確実に得点する」意識を持つことで、合格率は一気に上がります。
どんなに忙しくても、1か月前からの勉強で合格した人はたくさんいます。最後のひと踏ん張り、応援しています!
まとめ|宅建 勉強期間の目安と勉強時間
| 残り期間別の目安 | 内容まとめ |
|---|---|
| 6か月前(4月中旬) | 毎日2時間で基礎からじっくり。最も余裕を持って合格を狙える。 |
| 4か月前(6月中旬) | 標準ペース。過去問中心で効率を意識すれば十分合格可能。 |
| 3か月前(7月中旬) | 集中すればまだ間に合う。インプット3割・アウトプット7割で攻める。 |
| 2か月前(8月中旬) | 1日6時間ペースで短期決戦。過去問と模試中心で得点力を磨く。 |
| 1か月前(9月中旬) | 総復習期。新しい知識より“確実に取れる問題”を増やす。 |
宅建の勉強期間は、一般的に初学者で350時間・既修者で250時間が目安です。試験は10月中旬に行われるため、逆算して「4月中旬〜6月中旬」から始めるのが理想です。
とはいえ、7月や8月からでも、戦略と集中次第で合格は十分可能です。大切なのは「何を・どの順で・どれくらいやるか」を明確にすること。
まずはテキストをざっと読み、YouTubeで理解を深め、問題集を解く流れを作ってください。このサイクルが“短期合格”の王道です。
勉強は時間よりも「継続の質」で決まります。あなたの生活スタイルに合ったペースで、合格をつかみましょう。
試験の最新日程や公式情報は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)公式サイトをご確認ください。




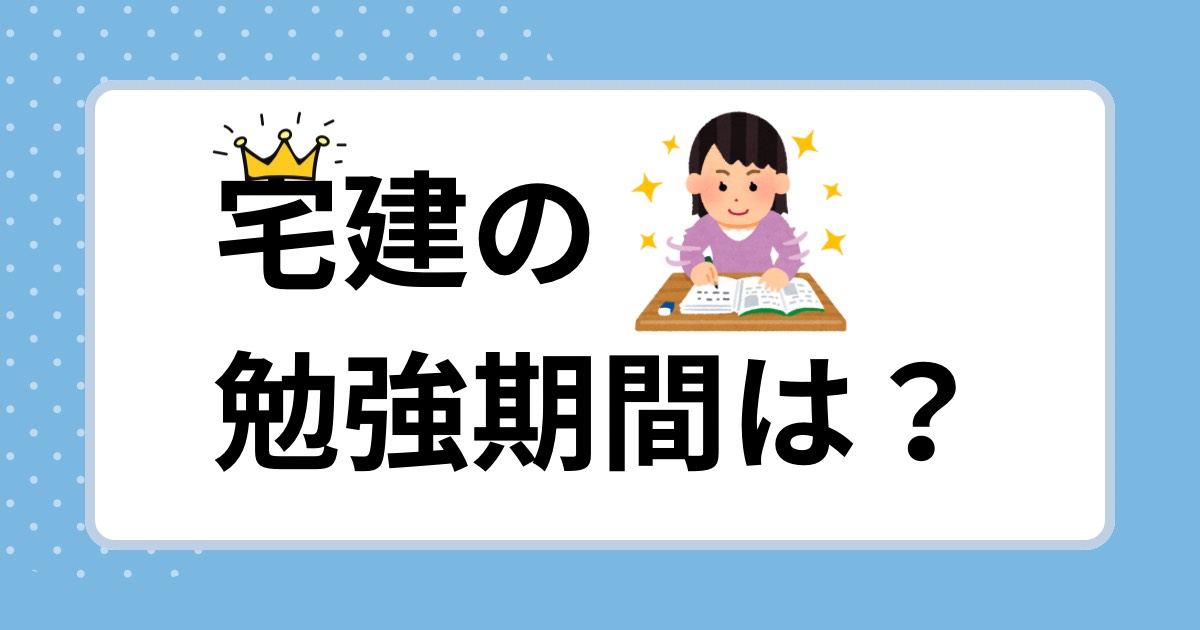
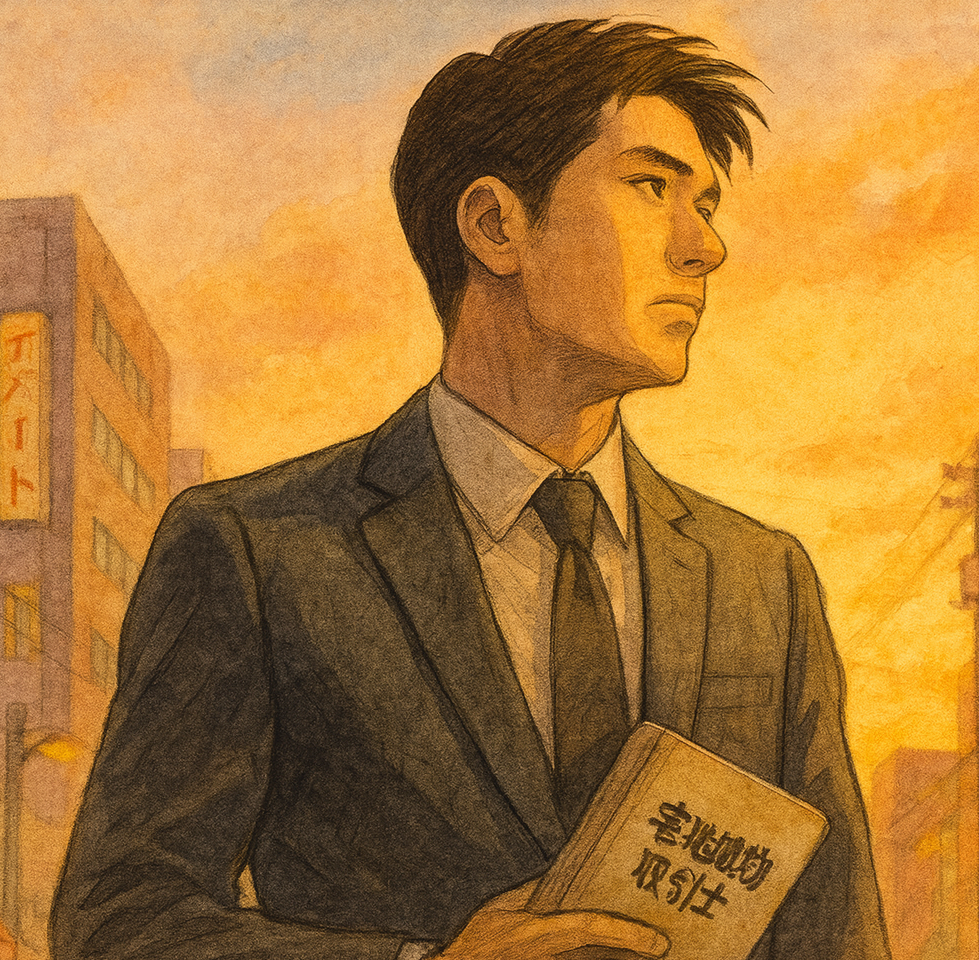
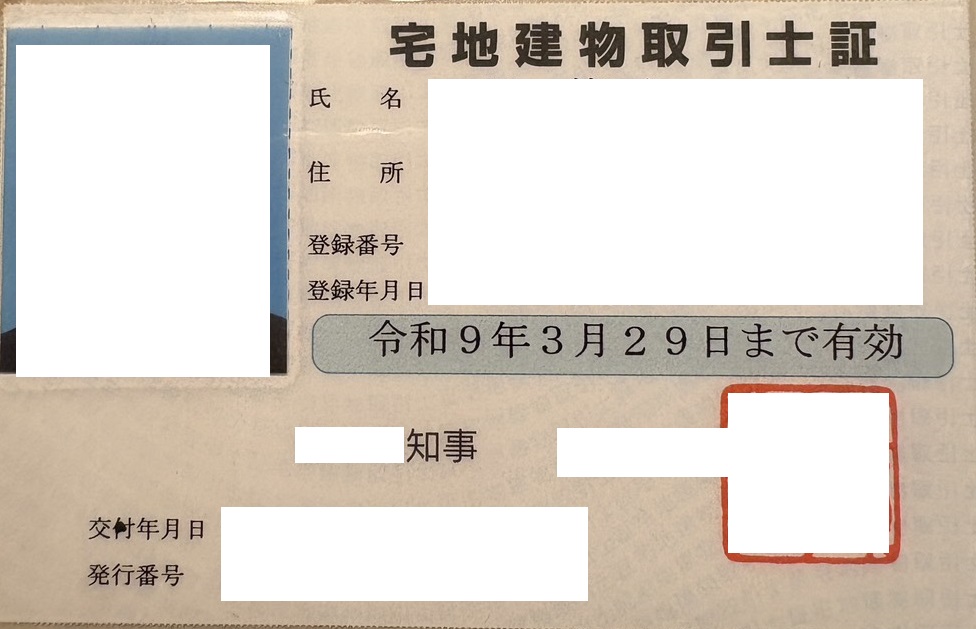







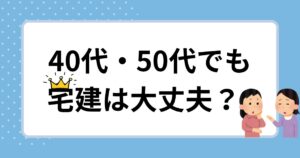

コメント