 新人くん
新人くん宅建は独学で合格できるのか?
結論から言うと、宅建は独学でも合格は可能です。ただし決して簡単ではなく、自己管理力や継続力が必要になります。実際に私も独学で合格しましたが、1回目は不合格を経験しました。
この記事では、宅建独学のメリット・デメリットから、おすすめ教材や勉強法、さらに私自身の体験談まで詳しく紹介します。特に不動産業界未経験の方は、通信講座を活用するのも有効な選択肢です。
最後まで読めば「独学でどう勉強を進めればいいか」、そして「独学が難しいと感じたときにどんな次の一歩を踏み出すべきか」が明確になります。
宅建は独学で合格できるのか
宅建は独学で合格できるのかについて解説します。
新人くん: 宅建って、独学だけじゃやっぱり無理なんですか?私は不動産業界も未経験なので不安で…。
タク: 無理ではありません。ただし簡単でもないんです。私は独学で合格しましたが、1回目は不合格でした。未経験の人は特に専門用語でつまずくので、通信講座を検討するのも選択肢ですよ。
①独学でも合格できる理由
宅建試験は毎年20万人以上が受験し、合格率は15〜17%前後で推移しています(出典:国土交通省 宅建試験実施概要、最終確認日:2025年9月)。
合格者の中には独学で挑戦した人も数多くいます。市販教材の質が向上していることや、YouTubeやネットで補足情報を得やすくなったこともあり、独学でも合格できる環境が整ってきました。
ただし「独学=楽に合格できる」という意味ではありません。私自身も1回目は独学で臨んで不合格。勉強の仕方や継続力が求められるのが現実です。
②合格率と勉強時間の目安
宅建合格に必要な勉強時間は300〜500時間が目安とされています。これは独学でも通信講座でも変わりません。
1日2時間の勉強を半年間続ければ約360時間。1日3時間なら540時間になります。数字だけ見れば社会人でも十分に到達可能な勉強量です。
ただし未経験の人は、用語の理解に時間を取られるため、独学だと500時間以上かかるケースもあります。この場合は通信講座を活用した方が効率的です。
③独学が向いている人と向かない人
独学に向いているのは「自己管理ができて毎日コツコツ勉強を続けられる人」です。逆に、スケジュール管理が苦手だったり、モチベーションが続きにくい人には不向きです。
特に不動産未経験者は「登記」「抵当権」「借地借家法」などの専門用語でつまずきやすいため、最初から通信講座でサポートを受ける方が早く理解できるケースも多いです。
私は不動産業界で働いていたので用語に多少馴染みがありましたが、それでも1回目は不合格でした。この経験からも「独学は可能だけど簡単ではない」というのがリアルな答えです。
宅建独学のメリットとデメリット
宅建を独学で勉強するメリットとデメリットを紹介します。
①独学のメリット(費用・自由度・どこでも学べる)
独学のメリットは大きく3つあります。
- 市販教材だけなら1〜2万円程度で済むため、費用を安く抑えられる
- 自分の生活リズムに合わせて勉強できる
- 自宅・カフェ・通勤時間など、場所を選ばずに勉強できる
私自身も独学中心で勉強し、テキストと過去問に絞ったので1万円前後しかかかりませんでした。働きながらでも「帰宅後に2時間」「通勤中にアプリで過去問」といった柔軟なスタイルで勉強できたのは独学ならではの強みでした。
②独学のデメリット(質問できない・モチベ低下・専門用語の壁)
一方で、独学にはデメリットもあります。
- 分からない部分を質問できる環境がない
- 情報収集に時間がかかる
- 一人だとモチベーションが続きにくい
- 不動産未経験者は専門用語でつまずきやすい
私も1回目の受験は「分からない部分を放置したまま進んでしまい」、23点で不合格でした。特に未経験の人は「抵当権」「借地借家法」などの専門用語の理解に時間がかかり、勉強が進みにくい傾向があります。
この点、通信講座なら質問できる環境が整っているため、効率的に学習を進められます。独学は費用面では有利ですが、継続できる自信がない人や未経験でゼロから学ぶ人には通信講座をおすすめします。
宅建独学におすすめの教材
宅建を独学で勉強するなら、教材選びが合否を大きく左右します。ここでは独学におすすめの教材を紹介します。
①市販テキストの選び方
独学の最初の一冊は「分かりやすさ」で選ぶのが鉄則です。特にフルカラーで図解が多いテキストは理解しやすくおすすめです。
定番は「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」や「スッキリわかる宅建士」シリーズ。初心者でも読みやすく、独学でも理解を深めやすい構成になっています。
ただし、未経験の方は専門用語の壁があるため、最初から通信講座の教材一式を使う方が効率的なケースもあります。
②おすすめ過去問集と問題集
宅建合格のカギは「過去問演習」です。試験問題は過去問の焼き直しが多く、解法パターンを覚えることが最短ルートになります。
私自身もLECの過去問集を繰り返し解いて合格しました。まずは過去問を徹底的にやり込み、その上で苦手を克服するために問題集を取り入れるのが効率的です。
③模試・予備校の公開テストの活用
独学の弱点は「自分の立ち位置が分からない」こと。そこで役立つのが模試や予備校の公開テストです。
模試を受けると得点力だけでなく、時間配分や本番の緊張感に慣れることができます。市販の模試問題集を使うのもありですが、可能なら公開模試を1回受けておくと安心です。
④おすすめYouTube
最近はYouTubeでも分かりやすい宅建講義動画が増えています。独学でも「講師の解説を聞く」ことで理解度が一気に高まります。
特に法律分野は文字だけでは理解しづらい部分も多いため、動画でイメージを掴んでからテキストに戻ると効率的です。
おすすめのYouTubeチャンネルは、別記事でまとめているので参考にしてください。


宅建独学の勉強法
宅建独学の勉強法を具体的に解説します。



教材は分かりましたけど、実際どんな流れで勉強すればいいんですか?独学だと順番が分からなくて不安です。



基本は「理解 → 演習 → 苦手克服 → 実力確認」だね。僕もこの流れで勉強したけど、未経験の人は途中でつまずきやすいので、通信講座を使うのも一つの手だよ。
①テキストとYouTubeを併用して理解
独学の最初のステップは「理解」です。テキストをいきなり読み込むより、YouTube講義で全体像をつかんでからテキストを読む方が効率的です。
理解できなかった部分はネットや辞書で調べながら補強していきましょう。未経験者はこの段階でつまずきやすいので、通信講座の動画講義を使うと理解が早まります。
②過去問を繰り返してパターンを覚える
宅建合格のカギは過去問です。出題傾向が安定しているため、過去問を繰り返すことで「解法の型」が身につきます。
私も最初は同じ問題を何度も間違えましたが、解き直すうちに「こういうときはこの条文」というパターンが自然と頭に入りました。
③問題集で苦手を克服する
過去問だけではカバーしきれない部分は、問題集で補強します。特に模試形式の問題集は弱点発見に役立ちます。
私自身も過去問だけでは点数が伸び悩みましたが、問題集を追加して苦手分野を強化したことで、合格点まで一気に伸ばせました。
④模試で実力を確認する
独学最大の弱点は「今の自分の実力が分かりにくい」こと。模試を受ければ、得点力や時間配分、本番の緊張感を体験できます。
市販の模試問題集でも良いですが、可能であれば予備校の公開模試を1回は受けることをおすすめします。僕も直前期に模試を受けて「あと何点足りないか」が分かり、勉強方針を修正できました。
宅建独学合格の体験談
宅建独学合格の体験談を紹介します。



実際に独学で合格した人の勉強スケジュールってどんな感じなんですか?僕もイメージをつかみたいです。



最初の挑戦では23点で不合格だったんだけど翌年に独学でリベンジして合格。ただ、僕は不動産業界で働いていたので用語の理解に少しアドバンテージがあったよ。未経験の方なら通信講座を利用する方が効率的だと思う。それか転職後に宅建取得もありだね。
①1回目は23点で不合格
私の1回目の受験は、直前期に少し頑張った程度で臨みました。その結果は23点。不合格でした。独学は自由度が高い分、勉強不足に気づかないまま本番を迎えるリスクがあります。
②4月から勉強を始め9月に本格化
翌年は4月から少しずつ勉強を始め、9月に本格化しました。平日は1〜2時間、休日は5〜6時間を集中して勉強にあてました。直前期は一気に追い込んで得点力を伸ばしました。
③平日・休日の勉強時間の工夫
平日は通勤電車の中で過去問アプリ、昼休みにテキストというようにスキマ時間を使いました。休日は午前にインプット(テキストや動画)、午後にアウトプット(過去問・問題集)というように時間を分けたのが効率的でした。
④働きながら独学で合格できた理由
私がほぼ独学で合格できたのは、次の3つを徹底したからです。
- 過去問中心の勉強を続けた
- 毎日少しでも教材に触れる習慣をつけた
- 直前期に集中的に追い込んだ
ただし、これは私が不動産業界で働いていて多少の知識があったから可能だった部分もあります。未経験者なら、通信講座を使った方が効率よく合格に近づけると思います。
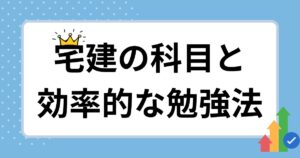
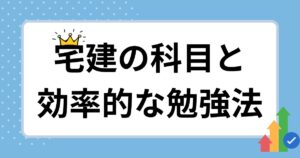


宅建独学が厳しいと感じた人へ
宅建は独学でも合格可能ですが、決して簡単ではありません。特に未経験者にとっては専門用語や法律の理解に時間がかかり、独学の難易度は高くなります。
①未経験で専門用語が難しい場合
不動産業界未経験の人にとって、宅建最大の壁は専門用語です。「抵当権」「借地借家法」「登記」などは最初は意味が分からず、独学だけだと理解にかなり時間がかかります。
この場合、通信講座の動画講義を活用すると、解説を聞きながら進められるので理解が早まります。
②独学が続けられないと感じる場合
宅建は半年以上の学習が必要になるため、独学ではモチベーション維持が大きな課題です。私自身も1回目は継続できずに不合格でした。
「一人でやると続かない」「計画的に進めるのが苦手」という人は、独学にこだわらず環境を変えるのも有効です。
③通信講座や勉強方法記事を参考にする選択肢
独学で挫折するリスクを減らすなら、通信講座を検討するのもおすすめです。質問できる環境や添削指導があることで、理解がスムーズになり合格までの道のりが短くなります。
また、「独学・通信・通学のどれが良いか」をまとめた記事もあるので、勉強スタイルに迷っている方はそちらも参考にしてください。
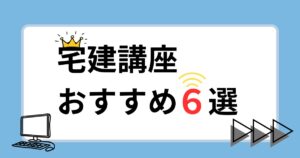
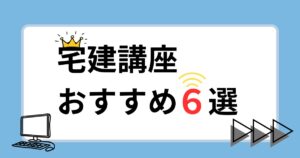
まとめ|宅建は独学で挑戦できるが効率も考えよう
| 独学で確認すべきポイント |
|---|
| 独学でも合格できる理由 |
| 必要な勉強時間と合格率 |
| 独学が向いている人と向かない人 |
宅建は独学でも合格できます。ただし誰にでも向いているわけではありません。自己管理力がある人は独学で進められますが、未経験者や一人だと続けられないタイプの人は通信講座を活用した方が効率的です。
私自身は独学で合格しましたが、1回目は不合格でした。独学は費用面では魅力的ですが、質問できない環境は想像以上にハードルが高いです。
逆に通信講座は費用はかかるものの、カリキュラムやサポートがあるので「最短で合格したい人」や「不安を抱えたまま進めたくない人」には向いています。
大切なのは「自分がどちらのタイプか」を見極めること。独学に挑戦するなら教材を絞って徹底的にやり込む、難しいと感じたら通信講座へ切り替える。この柔軟さが合格への近道になります。


出典:国土交通省 宅建試験実施概要(最終確認日:2025年9月)
出典:Indeed.jp – 宅地建物取引士の給与(最終確認日:2025年9月) ※求人ベースのデータであり、公的統計とは異なる可能性があります




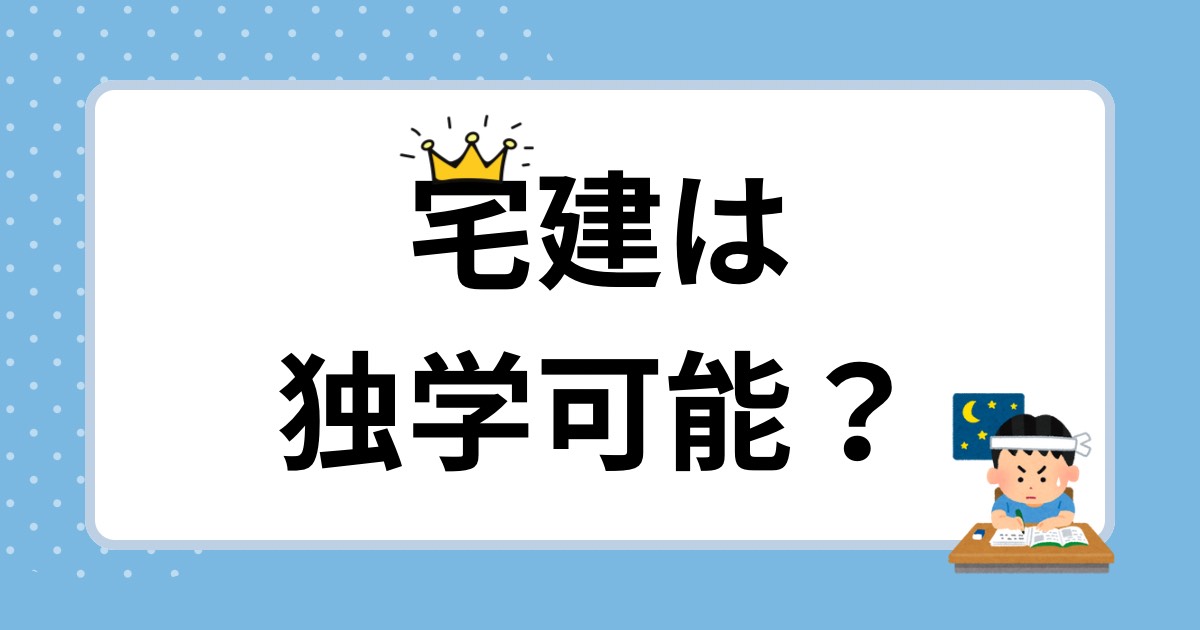
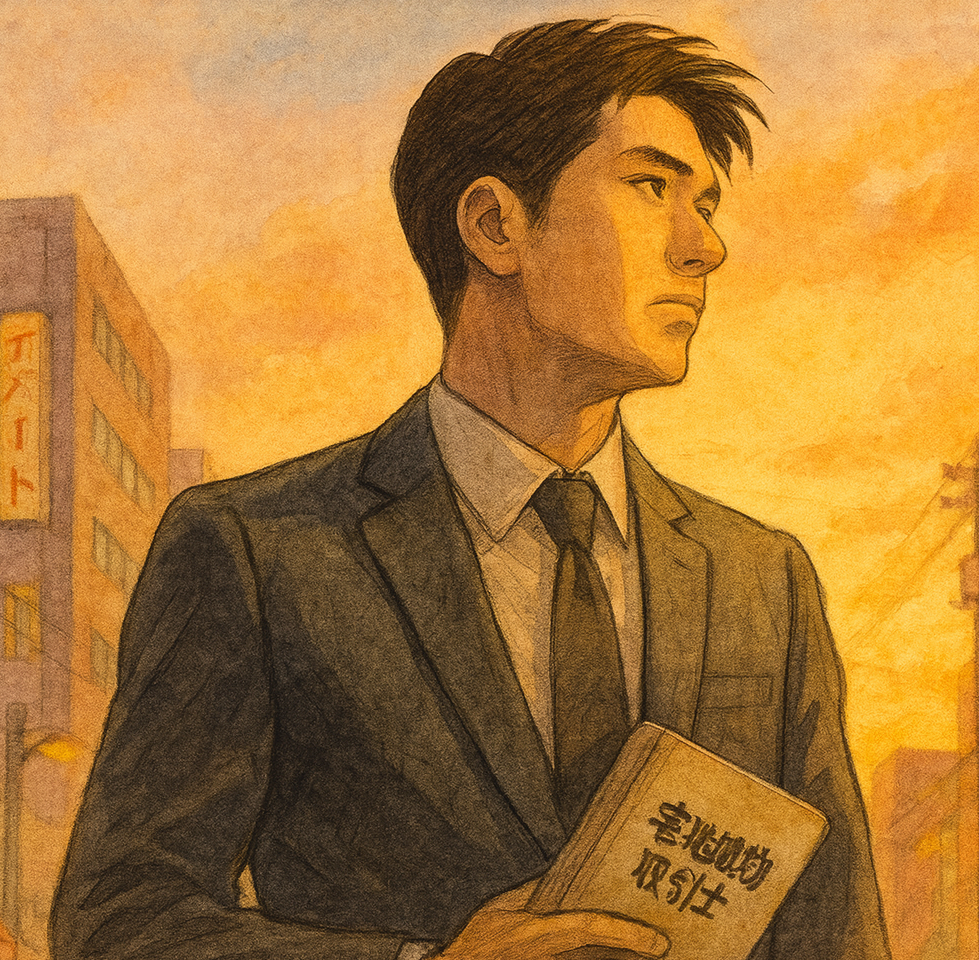
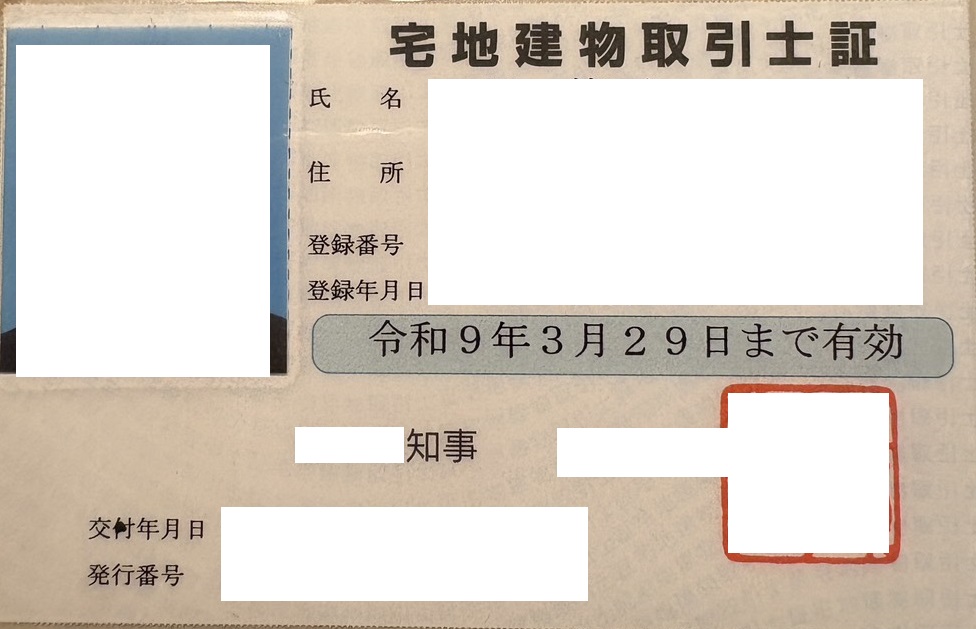








コメント