新人くん「宅建士を取ったら、次はどんな資格がいいんですか?」
タク「うん、いい質問だね。宅建を持ってる人なら“ダブルライセンス”を意識するといいよ。」
この記事では、宅建士と相性の良い資格を5つ紹介します。
特に注目したいのが、法務のプロである行政書士との組み合わせ。
不動産と法律の両面に対応できる“最強の組み合わせ”として人気です。
ただし、宅建と同時並行での勉強はおすすめしません。
まずは宅建をしっかり合格してから、次の資格にステップアップするのが現実的です。
この記事を読めば、「どんな順番で資格を取ればいいか」「自分に合うダブルライセンスはどれか」がスッキリわかります。
不動産業界でキャリアを伸ばしたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。
宅建士とダブルライセンスで相性のいい資格5選
宅建士とダブルライセンスで相性のいい資格について紹介します。
宅建士と相性の良い資格は、不動産業界や法律分野に関係するものが多いです。
どれも専門知識を広げて「仕事の幅」を広げるのに役立ちますよ。
①ファイナンシャルプランナー(FP)
FPは、宅建士とのダブルライセンスで最も人気のある資格のひとつです。
理由は簡単で、「お金の話」と「不動産の話」は切っても切れない関係にあるからです。
例えば賃貸営業でも、住宅ローンや資産運用の相談を受ける場面があります。
FPの知識があるだけで、「この人、詳しいな」と信頼感が一気に上がります。
私自身もFP3級を学んだことで、お客様のローン相談に対して根拠を持って答えられるようになりました。
営業トークの説得力が変わるんですよね。
②管理業務主任者
管理業務主任者は、宅建士と非常に近い分野の資格です。
マンションの管理組合などに対して重要事項説明を行う資格で、宅建士と重なる法律も多いです。
実際、宅建の勉強をしていれば6〜7割の内容は被っています。
宅建合格後に「もう少し深掘りしてみたい」と思った人にはおすすめですね。
試験時期が12月なので、宅建(10月)に受かってすぐに挑戦する人も多いです。
③賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士は、宅建士とのダブルライセンスで実務的に最も活かしやすい資格です。
2021年から国家資格になったことで注目度も急上昇しました。
賃貸管理業務に携わる人にとっては「実務特化の資格」と言えます。
私も現場でオーナー様と話すときに、管理士の知識があると契約や修繕の話がスムーズに進むのを感じます。
実際の契約トラブルにも強くなりますよ。
④マンション管理士
マンション管理士は、難易度が高い資格ですが「専門家としての信頼度」が非常に高いです。
宅建士よりも管理組合や法律に深く踏み込む内容で、独立コンサルタントとして活躍する人もいます。
合格率は10%前後と低いですが、宅建の知識があれば基礎は共通しています。
「もう一段レベルアップしたい」「管理系の専門家を目指したい」という人には最適です。
⑤行政書士
行政書士は、宅建士とのダブルライセンスの中でも「最強クラス」と言われる組み合わせです。
不動産契約に関わる書類作成や、行政手続き(許認可申請など)を代行できるようになります。
宅建士が扱える範囲は「説明」までですが、行政書士は「作成」や「提出」ができるんです。
つまり、法律業務の“手続き面”までワンストップで対応できるようになるわけですね。
不動産+法務のダブルライセンスとして、独立や副業にも非常に強い資格です。
ただし、行政書士はかなり勉強量が多いので、宅建を取ってから挑戦するのが現実的ですよ。
宅建士を取ってからダブルライセンスに挑戦すべき理由
宅建士を取ってからダブルライセンスに挑戦すべき理由について解説します。
①宅建の学習量は想像以上に多い
新人くん「宅建とFP、同時にやっちゃおうと思ってます!」
タク「気持ちはわかるけど…宅建だけでも結構きついよ?」
宅建の試験範囲は、民法・宅建業法・法令制限・税・その他とかなり広いです。
特に初学者にとって民法は難関。理解するまでに時間がかかります。
私も最初の年は「FPもやろうかな」と思っていましたが、結果的に宅建だけで手一杯でした。
本業がある社会人なら、なおさら「一点集中」が合格への近道です。
②同時並行は挫折のリスクが高い
資格を同時に勉強すると、一見効率が良いように見えて実はリスクが高いです。
理由は「どっちつかず」になりやすいからです。
科目の多い宅建に加えて、FPや行政書士の勉強を並行すると、記憶の定着率が落ちます。
結局、どちらも中途半端になるケースが本当に多いです。
まずは宅建に集中して“合格体験”を積むことが、次の資格勉強へのモチベにもなります。
③段階を踏んだ方がキャリア設計しやすい
資格取得は「順番」も大事です。
宅建に合格してから、実務を通して自分の得意分野を見つけ、その上で次の資格を選ぶ方が効率的です。
不動産管理に興味が出たなら「賃貸不動産経営管理士」、法律を深めたくなったなら「行政書士」。
目的が明確になってから勉強すると、結果的に早く合格できます。
宅建士と行政書士を組み合わせる強み
宅建士と行政書士を組み合わせる強みについて解説します。
行政書士は宅建士と並行して学ぶのは難しいですが、資格としての“相性”は抜群です。
不動産と法務をつなぐことができる、まさに「ダブルエンジン」的な組み合わせなんですよね。
①不動産契約と行政手続きの両方に対応できる
宅建士の仕事は、主に「契約の説明」や「重要事項の交付」に関する部分が中心です。
一方で、行政書士は「契約書の作成」「各種許認可申請」「法務手続き」に関われる資格です。
この2つを組み合わせることで、不動産に関する法務業務を“ワンストップ”で完結させることが可能になります。
例えば、土地売買の契約説明を宅建士として行い、その後の農地転用申請や開発許可申請を行政書士として対応する、という流れです。
現場では「別の士業に依頼する手間」が省けるため、お客様からの信頼もぐっと高まります。
新人くん「それってつまり、顧客にとってもメリットが大きいってことですね?」
タク「そう。依頼が“完結できる人”って、それだけで選ばれる理由になるんだよ。」
②独立開業や副業で活かせる幅が広い
宅建士と行政書士を持っていると、将来的な独立開業にも非常に強いです。
不動産業の免許を取るには、専任の宅建士が必要です。
さらに行政書士の資格を活かして、契約書作成・行政手続き代行・許認可サポートなどを業務に組み込めます。
つまり、「不動産業 × 法務代行」のダブル収益構造が作れるわけです。
私の周りでも、宅建+行政書士で「開業して年収800万円超え」という方は珍しくありません。
もちろん努力は必要ですが、選択肢が増えるという点では最強のペアだと思います。
新人くん「副業にも使えるんですか?」
タク「うん、個人の契約サポートとか、行政手続き代行なら副業レベルでもできますよ。」
③法律知識が深まりキャリアの武器になる
行政書士の勉強をすると、宅建の知識がより立体的に理解できるようになります。
宅建で学ぶ民法・宅建業法は行政書士の試験範囲にも含まれており、内容が重なっています。
つまり、「宅建で基礎を固め、行政書士で応用を学ぶ」流れが一番効率的なんです。
宅建合格者なら、行政書士の法律科目の理解が格段に早くなります。
特に、契約書や権利関係の解釈を深めることで、実務でもトラブルを未然に防げるようになります。
私も契約書を読み解く力がついたことで、賃貸契約のトラブルをいくつも防げました。
「あ、この特約はリスクあるな」って直感的にわかるようになるんですよね。
こういう“実務で生きる知識”こそ、ダブルライセンスの本当の価値だと思います。
宅建士と他資格を選ぶときの考え方3つ
宅建士と他資格を選ぶときの考え方を紹介します。
①キャリアプランから逆算する
「資格を取る」ことが目的になってしまう人が多いですが、実は順番が逆です。
まず、「今後どんな働き方をしたいか」を考えるのが先です。
営業職で成績を伸ばしたいならFPや管理士、独立志向なら行政書士、といった感じで方向性を定めましょう。
自分のキャリアプランに合う資格を選ぶことで、勉強のモチベーションも維持しやすくなります。
②難易度と学習コストを考える
資格ごとに学習時間や費用が大きく異なります。
| 資格名 | 平均学習時間 | 合格率 |
|---|---|---|
| 宅建士 | 300〜400時間 | 15〜17% |
| FP2級 | 150時間前後 | 40%前後 |
| 管理業務主任者 | 200〜250時間 | 20%前後 |
| 行政書士 | 700〜900時間 | 10%前後 |
こうして見ると、行政書士はかなりの学習量が必要です。
宅建を取ってから取り組むことで、基礎知識を活かしながら効率的に進められます。
③実務での相性をチェックする
勉強するだけで満足せず、「現場でどう活かせるか」を意識することが大切です。
不動産管理の仕事なら管理士系、契約・法務なら行政書士、金融・投資系ならFP。
資格と業務の相性が良ければ、昇進や転職にも直結します。
自分の実務に“リンクする資格”を選ぶのがポイントですよ。
宅建士ダブルライセンス取得の勉強法
宅建士ダブルライセンス取得の勉強法について紹介します。
①まず宅建合格を優先する
ダブルライセンスを目指すなら、まずは宅建に集中しましょう。
宅建を土台にすると、他資格の理解スピードが段違いに上がります。
特に民法や契約関係は行政書士でも重複して出題されるため、先に宅建を取っておくのが得策です。
私も宅建合格後にFPと管理士を勉強しましたが、法令関係がすんなり入ってきました。
②通信講座をうまく活用する
働きながら資格を取るなら、通信講座のサポートは非常に助かります。
動画講義でスキマ時間に勉強でき、わからない部分をすぐ質問できるのが魅力です。
特に行政書士や管理業務主任者のような法律系資格では、独学だと疑問点が多く詰まりがちです。
通信講座を「自分専用の質問環境」として活用するのがコツです。
③働きながら効率的に学ぶコツ
社会人学習の鍵は「毎日少しずつ、確実に積み上げること」です。
1日1時間でも、半年続ければ180時間。積み重ねは侮れません。
私も通勤時間と昼休みを勉強に充てて、合格をつかみました。
“完璧主義より継続主義”を意識すると、勉強のストレスがかなり減りますよ。
まとめ|宅建士とダブルライセンスでキャリアの幅を広げよう
| 資格別の特徴まとめ |
|---|
| ファイナンシャルプランナー(FP):お金の知識を武器に営業トークが強くなる |
| 管理業務主任者:宅建知識をそのまま活かせる“姉妹資格” |
| 賃貸不動産経営管理士:管理業務で即実践できる国家資格 |
| マンション管理士:難易度は高いが専門性が抜群 |
| 行政書士:不動産+法務の最強タッグ。独立にも強い |
宅建士をベースに、他の資格を組み合わせることで“できる仕事”の幅は確実に広がります。
ただし、最初から二つ同時に狙うのは非現実的です。
まずは宅建を確実に取り、その知識と経験を土台に次の資格を選ぶのが賢いルートです。
特に行政書士とのダブルライセンスは、不動産業界の中でも別格の存在感を発揮します。
契約書作成や許認可手続きまで一貫して対応できるので、顧客からの信頼が圧倒的に高まります。
「働きながらでも宅建は取れる」。そして、合格後の道もあなた次第でどんどん広がります。
焦らず一歩ずつ、“キャリアの武器”を増やしていきましょう。




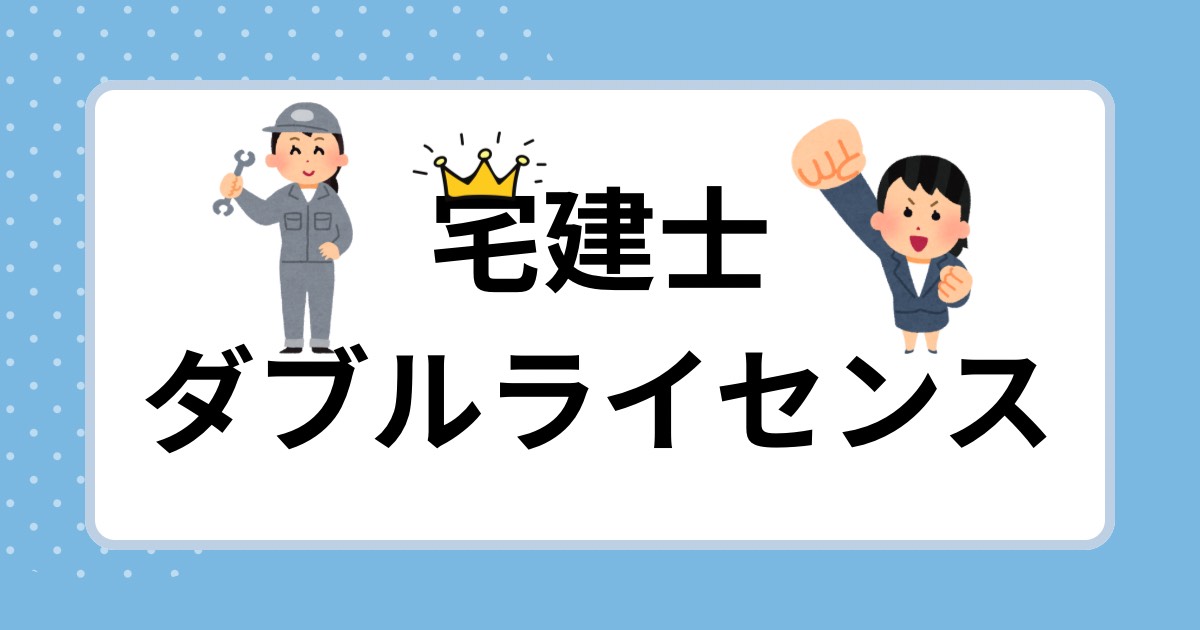









コメント