 新人くん
新人くん「宅建試験を受けるけど、いつも時間が足りなくて最後まで解ききれない…どうすればいいんですか?」
ネット上では「宅建は暗記ゲー」「いや、時間との勝負だよ!」など、受験生の声も二分されていますよね。
結論から言うと――時間が足りないと感じる人でも、戦略を変えれば合格ラインに届きます。
ただし、単に知識を増やすだけでは“時間との戦い”で勝てません。試験は120分という限られた時間のなかで、どれだけ効率よく回答できるかがポイントです。
そこで本記事では、
- 時間が足りないと言われる原因
- 秒単位で取り組むべき時間配分と実践ルート
- 試験中に焦らないためのメンタル&チェックポイント
を、実際に“時間に追われてきた”受験生の視点でわかりやすく解説します。
「最後まで解けなかった…」と後悔したくない方は、ぜひ最後までご覧ください。
宅建試験の制限時間と理想ペース
宅建試験は、限られた120分(登録講習修了者は110分)で全問題を解く「時間との勝負」です。
ここを数字で理解しておかないと、どんな勉強法も空回りします。
| 受験区分 | 試験時間 | 問題数 | 1問あたりの持ち時間 |
|---|---|---|---|
| 一般受験者 | 120分(13:00〜15:00) | 50問 | 約2分24秒 |
| 登録講習修了者(5問免除) | 110分(13:10〜15:00) | 45問 | 約2分26秒 |
つまり、1問に使えるのは“約2分20秒”前後。これを超えると、確実にどこかで詰まります。
時間配分のミスを防ぐには、あらかじめ「読む」「考える」「マークする」の時間を分解して考えるのがコツです。
| 工程 | 目安時間(1問あたり) | ポイント |
|---|---|---|
| 問題文を読む | 30〜40秒 | 設問の主語・否定語・条件だけ拾う |
| 考える・判断する | 60〜80秒 | 確実に分かる選択肢を先に処理する |
| マークする・チェック | 10〜15秒 | マークずれ防止。5問ごとに確認 |
このペースで回せれば、1問平均110〜120秒で完了。
50問×120秒=6,000秒(=100分)なので、残りの20分を「見直し」と「飛ばした問題」に充てられます。



え、1問2分ちょっとしか使えないんですか? それ、読むの遅い人もうアウトじゃないですか…。



最初から“全問均等”に時間を使う必要はないんだ。 むしろ、宅建は“時間を削れる問題”を最初に稼ぐ試験なんだよ。
たとえば、次のような戦略を立てると現実的です👇
例)
| 科目 | 問題数 | 理想時間 | 1問平均 |
|---|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | 30分 | 1分30秒 |
| 法令上の制限 | 8問 | 15分 | 1分52秒 |
| 税・その他 | 5問 | 10分 | 2分 |
| 権利関係 | 17問 | 55分 | 3分14秒 |
| 見直し | — | 10分 | — |
つまり、前半の「宅建業法+法令上の制限」で時間を貯金して、 後半の「権利関係」でその貯金を使うイメージです。



なるほど…最初に業法でリズム作って、後半にゆとり持たせるって感じか。



そう。焦るな。業法はサクサク取れるから、そこで15分早く終わらせたら勝ち。
- ✅ 宅建業法は「1問1分30秒以内」でリズムを作る
- ✅ 権利関係は「時間がかかる前提」で最後に回す
- ✅ 残り10分はマーク確認・飛ばし問題の再チェックに充てる
この時間感覚が身につくと、「焦って時間切れ」から一気に抜け出せます。
宅建は、120分を“どう使うか”の試験なんです。
宅建試験を時間内に解ききるコツ7つ
宅建試験を120分で解ききるためには、“感覚”ではなく“秒単位の戦略”が必要です。



毎回40問くらいで時間切れになるんですよ…。最後の10問、いつも塗り絵です。



あるあるだね。でも、時間が足りんのはスピードじゃなくて“順番と判断の問題”だよ。
| コツ | 内容 | 目安時間 |
|---|---|---|
| ①問題を解く順番を固定 | 毎回同じ流れで解くと脳の切り替えロスを防げる | 最初の30秒で「業法→法令→権利関係」の順を決める |
| ②迷った問題は即スキップ | 1分考えても分からない問題は飛ばす | 最大60秒で判断・マークして飛ばす |
| ③見直し時間を確保 | 最後の10分はマークずれ&逆選択の確認専用 | 10分を残しておく前提で進める |
| ④宅建業法から先に解く | 業法は得点源。1問1分半で20問を30分以内に終える | 30分以内に20問完了 |
| ⑤1問あたりの目安を決める | 科目ごとに時間配分を事前設定 | 業法1.5分/法令2分/権利3分 |
| ⑥マークミス防止法 | 5問ごとに番号確認&指で追う | 確認に1分追加で確実に |
| ⑦時計の位置を固定 | 右上にアナログ時計を置く。感覚で時間を読む | 残り時間の確認は20分・10分の2回でOK |
タクのメモ:
- 🕐 宅建業法で「スピード貯金」を作れ(30分以内)
- 🧭 1問で止まるな。飛ばす判断をルール化
- 🧠 10分見直しは絶対死守(マークずれで落ちる人多い)
- 📋 「業法→法令→権利」の順が最も安定
- ⏱ 時計を味方にする。時間を測るのも練習の一部



なるほど…“スピード貯金”って発想いいですね。最初に余裕作っとく感じですか。



宅建業法でリズム作って、権利関係で粘る。焦るんじゃなくて、走る順番を決めておく。
宅建は50問を戦略的に「解く順番」で勝つ試験。
1問ごとの速さよりも、“全体の流れ”を作ることが本当の時短術です。
宅建試験の時間配分を身につける練習法5つ
「勉強してるのに時間が足りない…」という人の9割は、“時間感覚の練習不足”です。
時間配分はセンスじゃなく、訓練で身につけるスキルなんです。



いや〜、過去問は解いてるんですけど、本番形式で時間測るのって面倒なんですよね…。



面倒くさがるやつが一番損する。時間配分は“慣れ”測らん練習は意味がないよ。
| 練習法 | 内容 | 目的・効果 |
|---|---|---|
| ①過去問を本番形式で解く | 50問を120分で一気に解く。机・時計も本番環境に近づける。 | 本番の集中力・ペース感覚を再現。弱点時間帯を把握。 |
| ②タイマーで時間感覚を養う | 20分・40分・60分ごとに進捗チェック。 | 「今どこまで進んだか」を体で覚える。焦りを防ぐ。 |
| ③60分で25問を解く練習 | 試験の前半を“タイムアタック”に設定。 | 残り60分で余裕が生まれる。後半の焦りを解消。 |
| ④模試で制限時間を徹底意識 | 模試を“時間の実験場”に。得点より時間感覚を重視。 | 本番さながらの緊張練習。リズムを崩さない訓練になる。 |
| ⑤苦手科目を先に潰す | 権利関係など、時間がかかる科目に先に慣れる。 | 本番で「読むのに時間がかかる」を防ぐ。 |
タクのメモ:
- ⏱ 過去問は「量」より「時間」を測ることに価値がある
- 📖 タイマー練習で“自分の体内時計”を育てる
- ⚡ 60分で半分解ける人=本番で焦らない人
- 🎯 模試は“時間訓練”と“焦り慣れ”のために使う
- 💥 苦手科目を先に潰して、時間配分のバランスを安定させる



つまり、時間配分は知識じゃなくて“身体感覚”ってことですね。



そうそう。宅建はマラソンや。タイムを測って走らんと、ゴールできへん。
時間配分を鍛えるには、「時間を測って勉強する」が絶対条件。 スマホのストップウォッチでもOK。時間と戦う練習が、合格を引き寄せます。
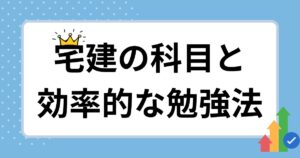
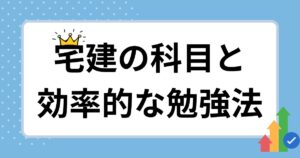
時間が足りない人のための勉強法6つ
「解くスピードが遅い」「読むのに時間がかかる」──その原因は、知識不足よりも“練習の仕方”にあります。
宅建は、知識量よりも“処理速度”を上げる勉強法で勝負する試験です。



いや〜、テキスト読んでも全然スピード上がらないんですよ…。覚えるのに時間かかるし。



テキスト読むのが勉強やと思ってる時点で遅い。宅建は読むより“反射”で答えられるようにせなあかん。
| 勉強法 | 内容 | 目的・効果 |
|---|---|---|
| ①アウトプット重視に切り替える | 読むより「解く」。問題→解説→再挑戦のサイクルを回す。 | 反応速度を上げる。1問にかかる思考時間を削減。 |
| ②一問一答で反射的に答える訓練 | ○×形式でテンポを上げる。1問5〜10秒で判断。 | 読解スピードと判断力を同時に鍛える。 |
| ③スキマ時間に短問を解く習慣 | 通勤・昼休みに3〜5問。スマホアプリを活用。 | 「毎日触れる」ことで忘却を防ぎ、反射力を維持。 |
| ④模試を週1ペースで解く | 週末に2時間タイマーを使って本番練習。 | 時間感覚と緊張耐性を同時に鍛える。 |
| ⑤宅建業法を最速で得点源にする | 業法20問を25分以内で解く訓練を重点化。 | “時間の貯金”を作り、後半に余裕を残す。 |
| ⑥「理解よりスピード」練習を意識 | 完璧に覚えるより、まず手を動かす。10問→間違い→再挑戦。 | 短期集中でスピードを上げ、実戦感覚を養う。 |
タクのメモ:
- ⚙️ 「読む→解く」に切り替える瞬間が成長のスタート
- 🎯 一問一答で“反射神経”を鍛えろ(考えすぎない)
- 📱 スキマ時間で「触れる頻度」を増やせ
- 🕐 模試で2時間通し練習→週1ルーティン化
- 💥 宅建業法でスピードを稼げば焦りは激減
- 🚫 理解完璧主義より“慣れ優先”が合格への近道



なるほど、テキスト読むより「体で覚える」って感じですね。



宅建はスポーツと同じ。頭で理解するんじゃなくて、手が勝手に動くまで練習するといいよ。
知識を増やすより、知識を“早く引き出す練習”を増やす。
時間が足りない人ほど、“スピード訓練”で勝ち筋が見えてきます。
宅建試験で焦らないメンタル管理法3つ
宅建試験で一番怖いのは、「焦って頭が真っ白になること」。 でも焦りは、根性じゃなく“整える習慣”で防げます。
体・心・思考の3つを整えることで、本番でも落ち着いて戦えます。
① よく寝る(身体を整える)
- 試験前日は夜更かし厳禁。6〜7時間は寝る。
- 22〜23時に寝て、翌朝しっかり頭を起こす。
- 「眠気」は最大の敵。寝不足は集中力を30%落とす。
- 前日は“新しい勉強”より“睡眠”が優先。
よく寝ることは、焦りを消す最も簡単で最強の方法です。 寝てる間に脳が情報を整理してくれるので、むしろ勉強より効果的です。
② ポジティブ自己暗示(心を整える)
- 焦ったときは「落ち着けば取れる」と心で唱える。
- 否定的な言葉は使わない。「やばい」は封印。
- 試験中に深呼吸3回。「今に集中する」意識を戻す。
- “自分を安心させる言葉”をひとつ決めておく。
脳は言葉に反応します。 不安な言葉を使えば焦りが増し、落ち着いた言葉を使えば冷静になります。 「焦るな」より「大丈夫」「できる」で、思考をポジティブ側へ戻すんです。



たしかに…「焦るな」って自分に言っても、余計焦りますね。



脳は否定形が苦手なんだ。「焦らるな」より「俺ならできる」に変えよう。
③ 時間配分で焦りを防ぐ(思考を整える)
- 事前に「区切りタイム」を決めておく(例:30分で15問)。
- 時計を見るのは「焦るため」じゃなく「ペース確認」のため。
- 1問あたりの目安は約2分20秒(50問120分換算)。
- 「残り10分で見直し」をルールにする。
焦りの正体は「時間が見えていないこと」。 時間を数値で把握しておくだけで、試験中の安心感は別物になります。
タクのまとめメモ:
- 🛌 まず体を整える。寝不足は焦りを呼ぶ。
- 💬 言葉で心を整える。「俺ならできる」が魔法のフレーズ。
- ⏱ 時間を整える。区切りタイムを決めて余裕を作る。
焦りは根性ではなく、準備で防げる。 この3つの“整える習慣”を身につければ、どんな試験でも落ち着いて戦えます。
まとめ|宅建試験で時間が足りない人でも合格できる戦略
焦りながら解いていた頃の自分に伝えたい。 宅建は知識量より、「時間と心のコントロール力」で勝つ試験です。
この2時間をどう使うか。 それが、あなたの合否を決めます。
✅ 宅建試験で時間を支配する3つの戦略
- ① 時間設計を決める: 各科目にかける時間を固定し、ペースを崩さない。
- ② 勉強法を変える: 読むより“解く”。反射で答える力をつける。
- ③ メンタルを整える: よく寝て、落ち着いて、区切りタイムを守る。
時間を設計すれば、焦りは消えます。 焦りが消えれば、集中が戻ります。 集中が戻れば、あなたの実力はそのまま点数になります。
タクのラストメモ
- 🕐 宅建は「速く」より「計画的に」解く試験。
- 💬 焦りそうになったら、深呼吸1回。呼吸が戻れば思考も戻る。
- 🧠 1問に2分、残り10分で見直し。この黄金リズムを守れ。
- 🔥 最後まで落ち着いて手を動かした人が合格する。



なんか、やっと“時間と戦う”感覚が掴めました。焦らずやってみます!



焦らんかったやつが勝つ。それが宅建や。
時間を制する者が、宅建を制する。 もう焦る必要はありません。 あとは、いつも通り解くだけです。






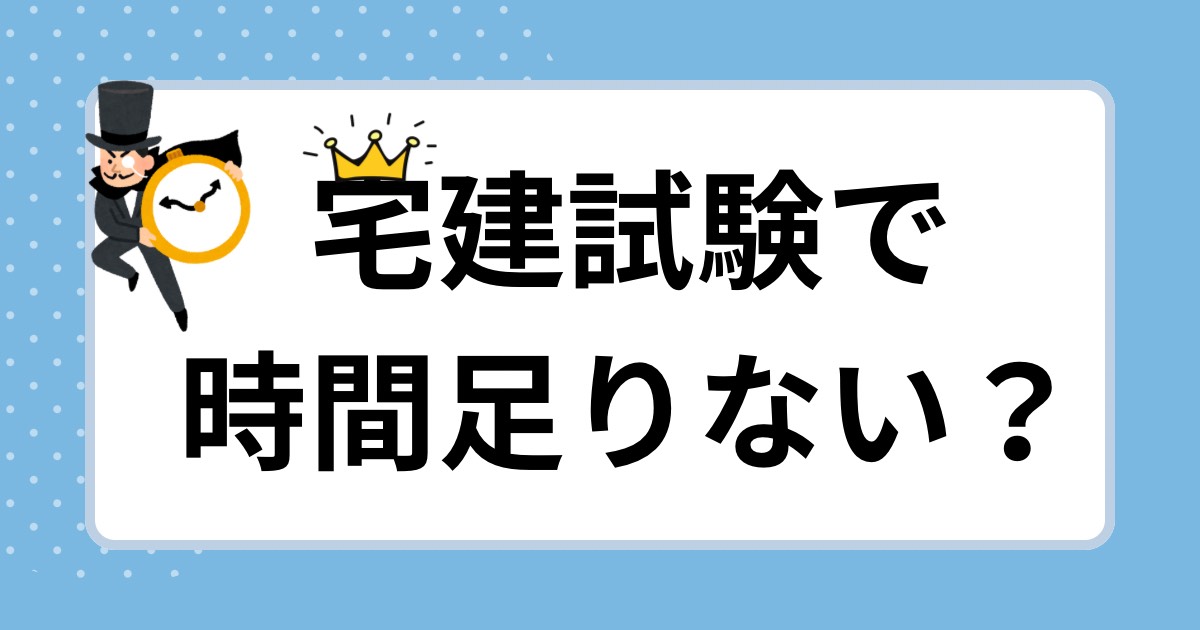
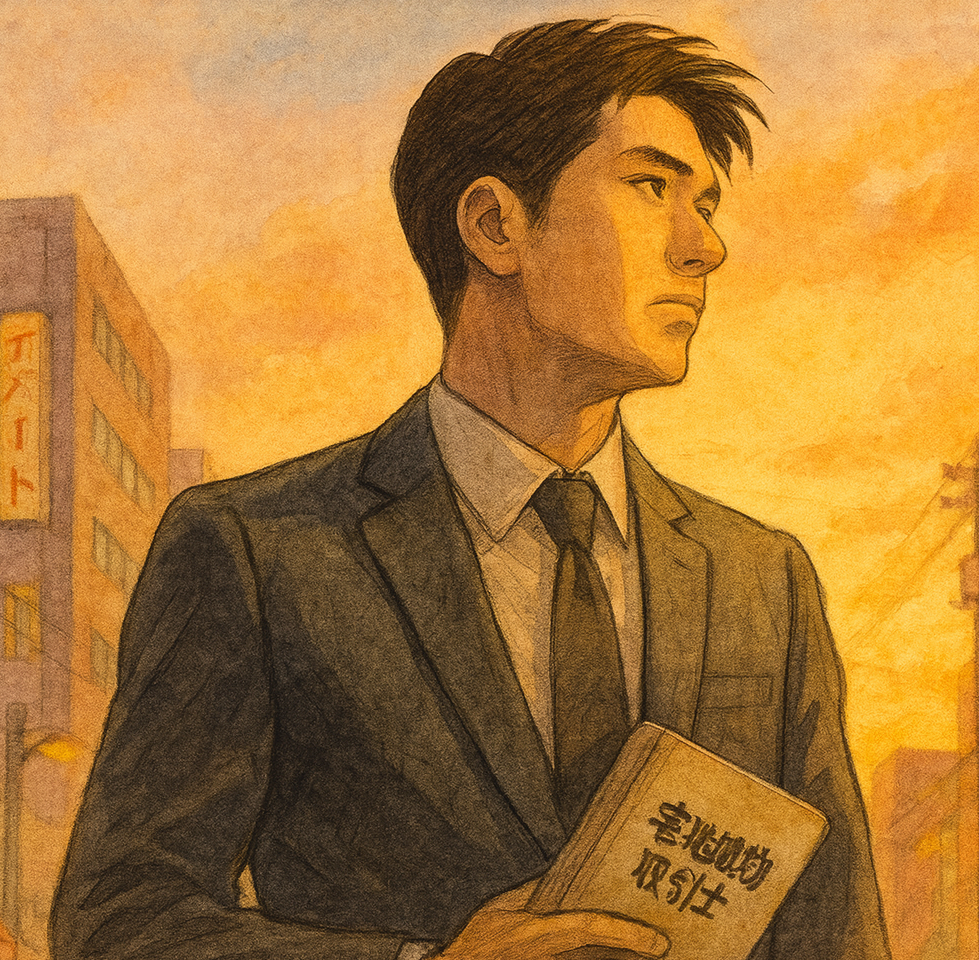
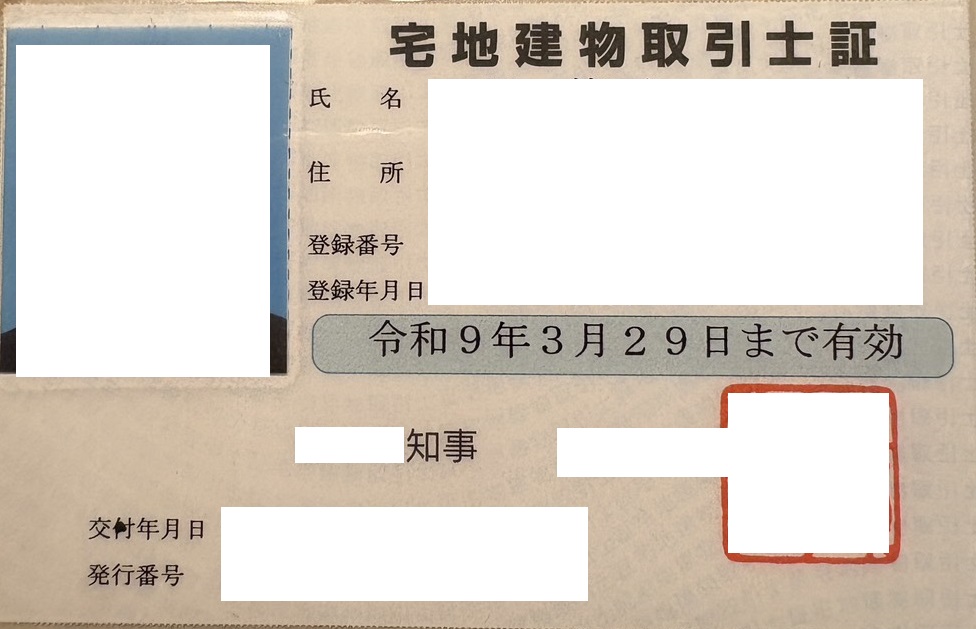









コメント