新人くん「宅建って取ったけど、正直どんな仕事で使えるんですか?」
タク「いい質問だね。実は“資格があるだけ”じゃ意味がない。どう使うかで人生が変わるんだよ。」
この記事では、「宅建士資格を活かせる就職先」や「企業がなぜ宅建士を求めるのか」を、現場目線でわかりやすくまとめました。
未経験から不動産業界を目指す人、転職でキャリアアップしたい人に向けて、実際に資格を活かせるリアルな職種や働き方を紹介します。
読めば、「自分の宅建資格をどこで活かすのが一番いいか」がはっきり見えてくるはずです。
宅建士資格を活かせる就職先7選【不動産業界中心に解説】
宅建士資格を活かせる就職先について、不動産業界を中心に紹介します。
- ①不動産仲介会社(売買・賃貸)※宅建士が必須の王道就職先
- ②不動産管理会社(契約書作成などで必要なケースあり)
- ③ハウスメーカー・建売会社(営業・契約担当)
- ④分譲マンションデベロッパー(販売・契約業務)
- ⑤リフォーム・リノベーション企業(施工+売買連携)
- ⑥不動産投資・コンサル企業(物件売買・顧客対応)
- ⑦賃貸仲介フランチャイズ本部・事業会社(研修・管理系職種)
それでは、それぞれの就職先について見ていきましょう。
①不動産仲介会社(売買・賃貸)※宅建士が必須の王道就職先
宅建士資格が最も直接的に必要とされるのが、不動産仲介会社です。 売買・賃貸いずれの分野でも「重要事項説明」や「契約書への記名押印」は宅建士の独占業務。 つまり、この業種では“持っていないとできない仕事”があるということです。
新人くん「やっぱり宅建って、仲介で一番活きるんですね?」
タク「そう。仲介は宅建士がいないと商売が回らない。法律的にも、営業的にもね。」
仲介会社では、売買と賃貸で業務内容が少し異なります。
| 分野 | 主な業務内容 | 宅建士の役割 |
|---|---|---|
| 売買仲介 | 物件案内・価格交渉・契約締結 | 重要事項説明・契約書署名 |
| 賃貸仲介 | 入居者対応・条件交渉・契約更新 | 契約説明・書類確認 |
特に売買仲介では「重要事項説明」を一人でこなせるかどうかが信頼度の分かれ目です。 お客様の前で堂々と説明できる宅建士は、それだけで“会社の顔”になれる存在です。 歩合の評価にも直結するケースが多く、営業職の中では最も資格が収入に反映されやすい業種ですね。
筆者の私も、営業時代に宅建を取ってから契約説明をすべて自分でできるようになり、 無駄な待ち時間が減りました。その結果、契約件数が増えて歩合が1.4倍になった経験があります。 やっぱり、宅建士を名乗れるかどうかは現場での信頼を左右します。
②不動産管理会社(契約書作成などで必要なケースあり)
不動産管理会社では、全員が宅建士を持っている必要はありません。 ただし、契約書を作成したり、オーナーと賃貸借契約を締結する場面では宅建士の知識が役立ちます。 特に「定期借家契約」や「管理受託契約」など、法的な書類を扱う業務では重宝されます。
また、管理会社では宅建士が1人以上在籍していることを求める会社も多く、 実際に「契約担当」や「リーシング課」に配置されるケースが一般的です。
新人くん「管理会社でも宅建って活かせるんですね?」
タク「そうだね。仲介ほど“必須”ではないけど、“持ってると任せられる”場面が多いよ。」
数字で見ると、宅建士手当がある管理会社は全体の約7割(出典:アガルート「宅建手当の相場」/最終確認日:2025年10月)。 専門性の高い部署に異動できるチャンスも増えます。
③ハウスメーカー・建売会社(営業・契約担当)
ハウスメーカーでは、宅建士が「営業+契約説明」を兼任するケースがあります。 特に建売販売では、不動産売買契約を自社で結ぶため、宅建士資格が必須になる場合もあります。
住宅ローンや登記に関する知識も求められるため、宅建士資格があることで顧客対応に厚みが出ます。 営業マンとしても、契約の流れを理解している人は提案の信頼性が段違いです。
④分譲マンションデベロッパー(販売・契約業務)
デベロッパーでは、モデルルームでの接客や販売契約が主な業務です。 契約を締結する際には宅建士による重要事項説明が必要となるため、資格保持者が担当することが多いです。
新人くん「販売職って華やかそうですね!」
タク「華やかだけど、契約時の責任は重いよ。宅建士の名前が入るってことは、法的に説明義務を負うからね。」
⑤リフォーム・リノベーション企業(施工+売買連携)
リフォーム系の会社でも、中古物件を扱う「買取再販事業」では宅建士が求められます。 中古住宅を買い取り、リフォームして再販売する流れでは、宅建業法が適用されるためです。
この分野では建築士と連携して仕事を進めることも多く、「宅建+建築の知識」を持つ人材は重宝されます。
⑥不動産投資・コンサル企業(物件売買・顧客対応)
不動産投資会社では、投資用マンションやアパートを販売する営業が中心です。 投資家への説明責任があるため、重要事項説明を行う宅建士の存在は欠かせません。
また、投資用物件の契約書や収益シミュレーションを扱う際も、宅建士の法的知識が信頼の裏付けになります。
⑦賃貸仲介フランチャイズ本部・事業会社(研修・管理系職種)
大手賃貸FC本部では、加盟店への研修担当や契約書チェック業務に宅建士資格が活きます。 現場よりも「教える・支える」側に回るキャリアを目指す人にも向いている分野です。
また、店舗開発や新規出店の審査業務など、バックオフィス系の仕事にも宅建士の知識は応用できます。
宅建士資格を活かせる就職先7選【不動産業界中心に解説】
宅建士の資格を取ったら、どんな仕事で使えるのか気になりますよね。
実はこの資格、使える場面がたくさんあります。でも、ぜったいに必要になる仕事は限られています。
いちばん必要とされるのは「不動産仲介の仕事」。それ以外は“知識として役立つ”仕事という感じです。
- ①不動産仲介会社(売買・賃貸)※宅建士が必須の王道就職先
- ②不動産管理会社(契約書を作るときに使うことがある)
- ③ハウスメーカー・建売会社(営業や契約のサポート)
- ④分譲マンションの販売会社(契約の説明をする仕事)
- ⑤リフォーム・リノベーション会社(中古住宅の販売など)
- ⑥不動産投資・コンサル会社(投資用マンションなどを扱う)
- ⑦賃貸仲介フランチャイズ本部(研修や書類のチェック)
それぞれの仕事で、宅建士がどんなふうに活かせるのか見ていきましょう。
①不動産仲介会社(売買・賃貸)※宅建士が必須の王道就職先
宅建士がいちばん活躍するのが「不動産仲介の仕事」です。
家を買いたい人と、売りたい人の間をつなぐ「売買仲介」、部屋を借りたい人を手伝う「賃貸仲介」があります。
新人くん「宅建って、仲介の仕事でそんなに大事なんですか?」
タク「そうだよ。宅建士がいないと契約の説明ができないんだ。だから会社にとっても、ぜったい必要な存在なんだよ。」
宅建士だけができる「重要事項説明」っていう仕事があります。 これは、お客さんに契約の大事な内容をしっかり説明することです。 つまり、宅建士がいないと家の契約ができません。
| 仕事の種類 | 主な内容 | 宅建士がやること |
|---|---|---|
| 売買仲介 | 家を売りたい人と買いたい人をつなぐ | 契約の説明・書類へのサイン |
| 賃貸仲介 | 部屋を借りたい人をサポートする | 契約内容の説明・確認 |
仲介の仕事では、宅建士がいると信頼されやすくなります。 お客さんの前で説明できる人は「この人なら安心」と思ってもらえるんです。
筆者の私も、宅建を取ってから契約を自分で説明できるようになって、仕事がスムーズになりました。 その結果、契約数が増えて、歩合給も上がりました。
宅建士は“信頼を得るための資格”と言ってもいいですね。
②不動産管理会社(契約書を作るときに使うことがある)
不動産の管理会社では、物件を持っているオーナーさんの代わりに建物を管理します。
宅建士の資格がぜったいに必要というわけではありませんが、契約書を作るときや更新手続きをするときには知識が役立ちます。
新人くん「管理会社でも宅建って意味あるんですか?」
タク「あるよ。宅建を持ってると、契約関係の仕事を安心して任せてもらえるんだ。」
会社によっては、契約担当やリーシング部門(入居者募集)に宅建士を置くところもあります。 宅建士がいると、法的なチェックを社内でできるからです。
③ハウスメーカー・建売会社(営業や契約のサポート)
家を建てて販売するハウスメーカーや建売会社でも、宅建士の知識は役立ちます。
とくに建売(すでに建っている家を売る)では、売買契約があるので宅建士が必要になることもあります。
営業マンが宅建士だと、お客様に説明できる内容が増えて信頼されやすくなります。 「家を売る人が契約にも詳しい」って安心ですもんね。
④分譲マンションの販売会社(契約の説明をする仕事)
マンションを販売する会社でも宅建士は大事です。 モデルルームで案内をして、気に入ってもらえたら契約へ。 そのときに「重要事項説明」が必要なので、宅建士が説明を担当します。
新人くん「販売の仕事って、キラキラしてそうですね!」
タク「そう見えるけど、実は責任が重いんだ。宅建士が説明した内容にミスがあると会社が困るからね。」
販売職では、説明をしっかりできる宅建士がとても重宝されます。
⑤リフォーム・リノベーション会社(中古住宅の販売など)
リフォーム会社でも、古い家を買って直して売る「買取再販」の仕事では宅建士が必要です。 このときは、リフォームよりも「売買契約」の部分で資格が使われます。
建築やデザインの知識と宅建をあわせ持っている人は、とても貴重です。 お客様にもわかりやすく説明できる人材として喜ばれます。
⑥不動産投資・コンサル会社(投資用マンションなどを扱う)
投資用のマンションやアパートを販売する会社でも、宅建士は欠かせません。
お客様(投資家)に契約内容を説明するとき、宅建士が説明を行います。 契約書の内容も複雑なので、資格を持っている人にしかできません。
営業よりも「契約を正しく進める」ことが大切な仕事です。
⑦賃貸仲介フランチャイズ本部(研修や書類のチェック)
「アパマンショップ」「ミニミニ」みたいなフランチャイズ本部にも、宅建士の仕事があります。
加盟店に対して教育をしたり、契約書のチェックをしたりと、現場を支える役割です。
新人くん「現場じゃなくても宅建って使えるんですね!」
タク「そう。宅建は“人に教える側”でも価値がある資格なんだ。」
この仕事では経験がある宅建士が活躍しやすく、安定した働き方ができます。
宅建士が企業から重宝される理由5つ【採用担当目線で分析】
宅建士の資格を持っていると、会社の中で「この人頼れるな」と思われやすいです。
どうして宅建士が企業にとって大事なのか、5つの理由でわかりやすく説明しますね。
新人くん「宅建士って、会社の中でそんなに大事なんですか?」
タク「そうだね。会社にとっても、お客さんにとっても“安心の証”みたいな存在なんだ。」
①契約業務を任せられる即戦力
宅建士がいると、会社は安心して契約の仕事を任せられます。
「契約書を作る」「お客さんに説明する」といった大事な場面で、会社の代表として動けるからです。
新人くん「資格があるだけで、そんなに違うんですか?」
タク「うん。宅建士は“法律のルールをわかってる人”として認められてるからね。」
宅建士がいれば、会社の信用もアップします。
②社内で「重要事項説明」が完結できる
宅建士だけができる仕事に「重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)」があります。
これは、家を買う人や借りる人に、契約の大事な内容を説明する仕事です。
もし会社に宅建士がいなかったら、外部に頼まないと契約ができません。
だから、宅建士が社内にいると「説明も契約も社内で終わる」ようになって、効率がグッと上がるんです。
③法令・書類対応の正確性が高い
宅建士は、宅地建物取引業法という法律を勉強しているので、書類をていねいに確認できます。
書類のミスって、契約トラブルのもとになることが多いんですよ。
タク「宅建を持ってる社員が書類を見ると、ミスが減る。これは会社にとってめっちゃ助かる。」
法律にくわしい人が社内にいると、トラブルの予防にもなるんです。
④顧客対応の信頼性が上がる(説明内容に説得力)
お客さんは、資格を持っている人の話のほうが安心して聞けます。
同じ内容でも、「資格を持ってる人が説明してくれた」というだけで信頼度が変わるんです。
新人くん「確かに、病院でも資格がある先生のほうが安心しますもんね。」
タク「そうそう。宅建士もそれと同じ。“説明の重み”が違うんだ。」
これは営業にも大きなプラスになります。 宅建士が説明すると「会社の信用」そのものが上がります。
⑤法定人数確保による免許維持に必要
不動産会社は、宅建士が一定の割合でいないと営業できません。
これを「法定人数」といって、会社が免許を持ち続けるための条件なんです。
| 宅建士の割合 | ルール |
|---|---|
| 5人に1人以上 | 宅建士でなければならない |
タク「だから宅建士が辞めると、会社はちょっと焦るんだよ。」
新人くん「会社を動かすために必要な人ってことですね!」
そう。宅建士は、会社にとって「法律的に必要な人」。 だからどの会社も、持ってる人を大切にするんです。
宅建士が企業から重宝される理由5つ【採用担当目線で分析】
宅建士の資格を持っていると、会社の中で「この人頼れるな」と思われやすいです。
どうして宅建士が企業にとって大事なのか、5つの理由でわかりやすく説明しますね。
新人くん「宅建士って、会社の中でそんなに大事なんですか?」
タク「そうだね。会社にとっても、お客さんにとっても“安心の証”みたいな存在なんだ。」
①契約業務を任せられる即戦力
宅建士がいると、会社は安心して契約の仕事を任せられます。
「契約書を作る」「お客さんに説明する」といった大事な場面で、会社の代表として動けるからです。
新人くん「資格があるだけで、そんなに違うんですか?」
タク「うん。宅建士は“法律のルールをわかってる人”として認められてるからね。」
宅建士がいれば、会社の信用もアップします。
②社内で「重要事項説明」が完結できる
宅建士だけができる仕事に「重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)」があります。
これは、家を買う人や借りる人に、契約の大事な内容を説明する仕事です。
もし会社に宅建士がいなかったら、外部に頼まないと契約ができません。
だから、宅建士が社内にいると「説明も契約も社内で終わる」ようになって、効率がグッと上がるんです。
③法令・書類対応の正確性が高い
宅建士は、宅地建物取引業法という法律を勉強しているので、書類をていねいに確認できます。
書類のミスって、契約トラブルのもとになることが多いんですよ。
タク「宅建を持ってる社員が書類を見ると、ミスが減る。これは会社にとってめっちゃ助かる。」
法律にくわしい人が社内にいると、トラブルの予防にもなるんです。
④顧客対応の信頼性が上がる(説明内容に説得力)
お客さんは、資格を持っている人の話のほうが安心して聞けます。
同じ内容でも、「資格を持ってる人が説明してくれた」というだけで信頼度が変わるんです。
新人くん「確かに、病院でも資格がある先生のほうが安心しますもんね。」
タク「そうそう。宅建士もそれと同じ。“説明の重み”が違うんだ。」
これは営業にも大きなプラスになります。 宅建士が説明すると「会社の信用」そのものが上がります。
⑤法定人数確保による免許維持に必要
不動産会社は、宅建士が一定の割合でいないと営業できません。
これを「法定人数」といって、会社が免許を持ち続けるための条件なんです。
| 宅建士の割合 | ルール |
|---|---|
| 5人に1人以上 | 宅建士でなければならない |
タク「だから宅建士が辞めると、会社はちょっと焦るんだよ。」
新人くん「会社を動かすために必要な人ってことですね!」
そう。宅建士は、会社にとって「法律的に必要な人」。 だからどの会社も、持ってる人を大切にするんです。
宅建士資格を活かしたキャリアモデル3パターン【現場リアル】
宅建士の資格は、取りっぱなしにしないでこそ本当の価値が出ます。
実際に仕事の中でどう活かせるか。どんなキャリアを築けるか。
ここでは、現場でよくある3つのキャリアモデルを紹介します。
新人くん「宅建って、取ったあとにどんな道があるんですか?」
タク「それが一番大事なとこ。資格は“取る”より“どう使うか”なんだよ。」
①営業職→主任者→店長・支店長(不動産業界の王道ルート)
不動産の世界で最も多いのがこのパターンです。
宅建を持っていないと「主任者」になれない会社が多く、昇進のスタートラインが変わります。
営業として結果を出しても、資格がないと昇格できないケースもあります。 だからこそ宅建士を持っている人は、評価されやすくチャンスが広がるんです。
筆者の私も営業時代、宅建を取った年に契約数が増えて、上司から「じゃあ次は主任やな」と言われた経験があります。
| 段階 | 役職 | 仕事内容 |
|---|---|---|
| Step1 | 営業担当 | 物件案内・契約準備 |
| Step2 | 主任者 | 契約説明・後輩育成 |
| Step3 | 店長・支店長 | 店舗運営・マネジメント |
新人くん「宅建があるだけで主任に上がれるって大きいですね!」
タク「そう。実務ができるのはもちろん、会社としても“資格を持ってる人が上に立つ”ほうが安心だからね。」
②事務職→契約担当→管理職(女性にも多い安定コース)
宅建士は、営業だけでなく事務職にも強い資格です。
契約書の作成やチェック、重要事項説明の準備など、正確さが求められる仕事で力を発揮します。
事務職スタートでも、宅建を持っている人は「契約担当」や「管理部門」にキャリアアップしやすいです。 特に女性社員で宅建士を取る人は増えていて、会社の中でも頼られる存在になっています。
タク「契約書を自分で見られる人は、現場でも強い。宅建士は“事務のプロ”にもなれる資格なんだよ。」
実際に、宅建士を持っている人は、総務や法務のポジションに異動するケースもあります。 「営業ほどガツガツはしたくないけど、安定した仕事をしたい」という人にはピッタリの道です。
③未経験→宅建取得→業界転職→年収UP(キャリアチェンジ型)
まったくの未経験からでも、宅建士を取って転職する人は多いです。
特に異業種から不動産業界に入る場合、宅建があると「基礎知識がある人」として採用されやすくなります。
新人くん「未経験でも通用するんですか?」
タク「通用するよ。宅建を取る努力ができる人は、会社も伸びると思ってくれるんだ。」
最初はアシスタントや営業サポートからのスタートでも、経験を積めばしっかり評価されます。 また、宅建手当がつく会社も多く、資格を持っているだけで月に1万円〜2万円ほど給料が上がることもあります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| Step1 | 宅建の勉強を始める(働きながらでもOK) |
| Step2 | 資格を取って、転職サイトやエージェントに登録 |
| Step3 | 業界で実務経験を積み、キャリアを広げる |
このルートは「努力を成果に変える」道。 資格を取って終わりではなく、それをどう活かすかで未来が変わります。
筆者の経験でも、宅建を取ってから転職を決めた同僚は、年収が60万円以上上がったケースもありました。 会社側も「教育コストがかからない人材」として、採用しやすいんです。
宅建士は「キャリアチェンジに強い資格」。 努力がしっかり報われる数少ない国家資格だと思います。
宅建士資格を活かした転職を成功させるコツ【おすすめエージェント紹介】
宅建士の資格を取ったあと、「せっかくならもっと良い会社に行きたいな」と考える人も多いです。
でも、どんな求人を選べばいいのか分からない人も多いはず。 ここでは、転職をうまく進めるための考え方を3つだけ紹介しますね。
①宅建士の求人に強い転職エージェントを使う
転職を考えるなら、宅建士の求人を多く扱っているエージェントを使うのがおすすめです。
一般的な転職サイトよりも、不動産業界に特化したエージェントのほうが情報が早く、非公開求人も多いです。
タク「営業マン目線で言うと、“業界を知ってる担当者”に相談できるかどうかが一番大事。」
新人くん「たしかに、話が通じないと相談もしづらいですもんね。」
登録自体は無料なので、気になる会社があったら複数登録して比較してみるのがベストです。
②“資格手当”より“職務内容”で選ぶのがコツ
転職先を選ぶときに「宅建手当がいくらもらえるか」で決める人もいますが、 本当に大事なのは「どんな仕事を任せてもらえるか」です。
資格を活かして契約や説明に関わる仕事ができる会社なら、スキルが磨かれて将来のキャリアにもつながります。
タク「手当も大事だけど、経験はもっと大事。将来の自分の給料を上げてくれるのは“経験”だからね。」
企業選びでは、仕事内容・職場の雰囲気・教育制度などもあわせてチェックしましょう。
③現役営業マンおすすめの転職エージェントを紹介(別記事リンク)
「具体的にどのエージェントがいいの?」という人向けに、 別記事で“宅建士向け転職エージェント”をくわしくまとめています。

新人くん「やっぱり実際に使った人の意見がいちばん助かりますね。」
タク「そうそう。リアルな使い心地がわかると、安心して登録できるからね。」
宅建士の資格を活かした転職は、早めに動いた人ほどチャンスをつかみやすいです。 今の会社に不安がある人は、情報収集だけでもしておくといいですよ。
まとめ|宅建士資格を活かせる仕事を選べばキャリアが広がる
| 就職先のタイプ | 宅建士の主な活かし方 |
|---|---|
| 不動産仲介会社 | 契約説明・営業の中心となる仕事。宅建士が必須。 |
| 不動産管理会社 | 契約書の作成や法令チェックで知識を活かす。 |
| ハウスメーカー・建売会社 | 営業+契約のサポートで信頼を得る。 |
| 分譲マンション販売会社 | 重要事項説明など、宅建士が説明を担当。 |
| リフォーム・リノベ会社 | 中古住宅の買取再販など、売買契約で資格を使う。 |
| 不動産投資・コンサル会社 | 投資物件の契約説明・法的知識で信頼を得る。 |
| 賃貸仲介フランチャイズ本部 | 研修や書類確認など、裏方として会社を支える。 |
宅建士の資格は、不動産業界で「持っているだけで信頼される」資格です。
とくに仲介会社では必須資格として扱われるため、就職や転職を考えるなら最もおすすめの分野です。
一方で、管理会社やハウスメーカーなどでは、法律知識をもとに安心感を生む“プラスの資格”として活かせます。
資格を取って終わりではなく、どう仕事に使うかが本当の勝負です。
もし「自分に合う働き方」を見つけたい人はこちらも参考にしてください。
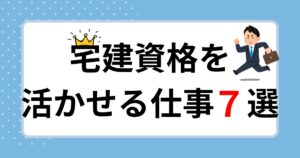
宅建士の資格は、あなたのキャリアを広げるための“最初の武器”になります。
出典:アガルート「宅建手当の相場」/最終確認日:2025年10月




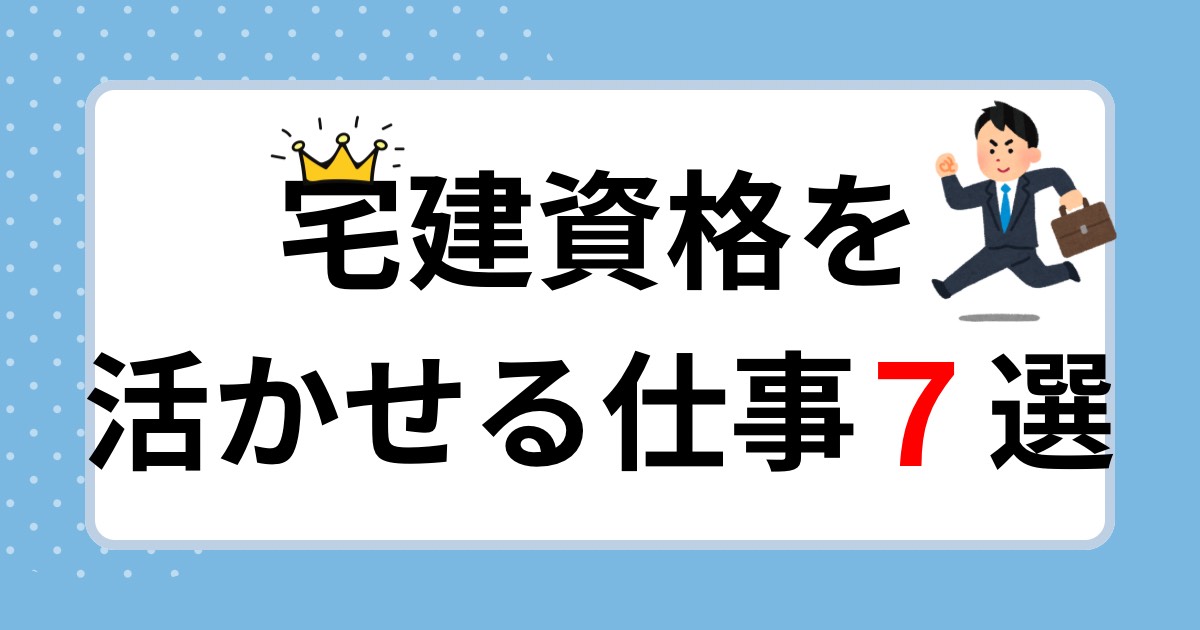








コメント