新人くん「宅建って、どの科目から手をつけたらいいんですか?」
タク「順番を間違えると、勉強が遠回りになるんだよ。」
宅建試験は「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「税・その他」の4科目で構成されています。
それぞれ出題の特徴がまったく違うため、効率的に進めるには“順序とバランス”が大切です。
この記事では、現役の賃貸営業マンである私タクが、
実際に働きながら合格した経験をもとに、4科目の勉強手順とコツを解説します。
「どこから勉強を始めればいいのか」
「何を優先すべきか」
この2つがわかれば、宅建の勉強はぐっと楽になります。
宅建試験の科目は4つ!まず全体像をつかもう
新人くん「宅建の勉強って、何を覚えたらいいのか全然わからないです…」
タク「そこだね。まず“何を勉強する試験なのか”を知るのが最初の一歩だよ。」
宅建試験は、次の4つの科目で構成されています。
| 科目 | 出題数 | 主な内容 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | 免許制度・契約ルール・取引士の義務など | 得点源。最重要科目。 |
| 権利関係 | 14問 | 民法・借地借家・契約・相続など | 理解が必要。難易度高め。 |
| 法令上の制限 | 8問 | 都市計画法・建築基準法・国土利用計画法など | 数字暗記中心。 |
| 税・その他 | 8問 | 固定資産税・不動産登記法・地価公示法など | 短期攻略可。 |
合計50問のうち、宅建業法だけで20問出ます。 つまり、全体の4割。まずここを取らなきゃ始まりません。
タク「業法は点が取りやすく、民法は時間がかかる。法令と税は暗記で固める。バランスが大事だね。」
このあと、それぞれの科目ごとに“どう勉強すれば効率がいいか”を解説します。
宅建業法|最初に攻略すべき“得点源”
宅建業法は試験の軸です。出題数は20問。ここを安定させることで合格が近づきます。
① 出題内容と特徴(20問)
免許制度、重要事項説明、報酬上限、クーリングオフなど、実務に直結する内容が中心です。
宅建業法は「暗記+理解」のバランス型で、出題傾向が安定しています。
② 効率的な勉強法(過去問中心)
宅建業法は過去問がそのまま繰り返し出題されやすい分野です。
テキストで1周読んだあと、過去問を3周以上解くのが理想です。
出題パターンを体で覚えるイメージですね。
③ 実務とリンクして覚えるコツ
契約時に使う書類や業務の流れとリンクさせて覚えると、暗記が定着します。
タク「俺は実際の契約書をコピーして“条文の意味”をメモしてた。理解が深まるよ。」
権利関係(民法など)|理解力がカギを握る
宅建の“山場”がこの権利関係。出題数は14問。民法や借地借家、相続などが範囲です。
① 出題内容と特徴(14問)
抽象的な概念が多く、暗記だけでは対応できません。 法律的な思考を求められるため、得点が伸びにくい人が多いです。
② 難問を避けて得点源にするコツ
宅建では「全問正解」は不要。14問中、8問正解できれば合格ラインです。
契約・意思表示・代理などの“頻出テーマ”に絞りましょう。
③ 苦手を克服する現場的アプローチ
タク「民法はイメージで覚えるのがコツ。俺は“売主=A、買主=B”でストーリー化してた。」
法律用語に慣れるまでは、YouTube講義などを活用して耳から入れるのもおすすめです。
法令上の制限|数字と規制で点を取る
法令上の制限は8問。 暗記中心で、出題パターンが決まっているため、短期間でも得点が伸ばしやすい科目です。
① 出題内容と特徴(8問)
都市計画法、建築基準法、国土利用計画法などが中心。 似た言葉が多いため、数字や単位で整理することが重要です。
② 効率よく暗記する方法
・過去問を見ながら数字だけをノートにまとめる ・「用途地域」「建ぺい率」「容積率」などを表で比較する ・「10年」「3年」など期間の違いを意識して覚える
③ 業法とのつながりで理解を深める
法令と業法はセットで出題されることも多いです。
例えば「宅地」と「建築物」に関する定義を業法と照らして覚えると、理解がスムーズになります。
税・その他|短期間で仕上げる得点ゾーン
税・その他は8問。固定資産税・不動産登記法・地価公示法などが範囲です。
① 出題内容と特徴(8問)
出題範囲が広いですが、出るテーマは毎年ほぼ固定。暗記で対応可能です。
② 暗記で差をつけるテクニック
・税率・控除額は数字カード化して通勤中に覚える ・出題範囲が狭いので、1週間でも十分得点アップ可能 ・過去3年分を繰り返せば十分カバー可能
③ 直前期にスコアを伸ばす戦略
タク「試験1ヶ月前に“税・その他”を集中でやるのがベスト。忘れても短期間で戻るからね。」
短期記憶向きなので、直前期に仕上げておくと全体のバランスが整います。
効率的に4科目を勉強するための流れ
ここまでの内容を踏まえて、4科目をどう進めれば効率がいいかを整理します。
① 勉強順序の鉄則「業法→法令→権利→税」
最初に業法で点を稼ぎ、法令で得点を積み、民法で最低ラインを確保。 税・その他で仕上げる。この流れが最も再現性があります。
② テキスト→過去問→模試の学習サイクル
・テキストは「概要理解」用(1周だけ) ・過去問で「出題パターン」学習(3〜5周) ・模試で「本番慣れ」+「弱点発見」
③ 3つの落とし穴とその回避法
- 民法に時間をかけすぎる → 「業法で稼ぐ」意識を持つ
- 過去問を暗記だけで終える → 「理由説明」をノートに書く
- 模試を受けずに本番を迎える → 「緊張慣れ」不足でミスが出やすい
タク「完璧を目指すより、“取れる問題を確実に取る”が大事だよ。」
まとめ|4科目を地図でとらえれば合格は近い
宅建試験は、4科目をバランスよく攻略すれば合格ライン(35点前後)に届きます。
| 科目 | 出題数 | 勉強のポイント |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | 最初に得点源を作る |
| 権利関係 | 14問 | 難問を避けて頻出テーマに集中 |
| 法令上の制限 | 8問 | 数字暗記でスコアを安定 |
| 税・その他 | 8問 | 直前期に短期集中で伸ばす |
新人くん「全体の流れが見えたら、なんかできそうな気がしてきました!」
タク「そう、それがスタートライン。科目を地図でとらえれば、迷わず進めるよ。」




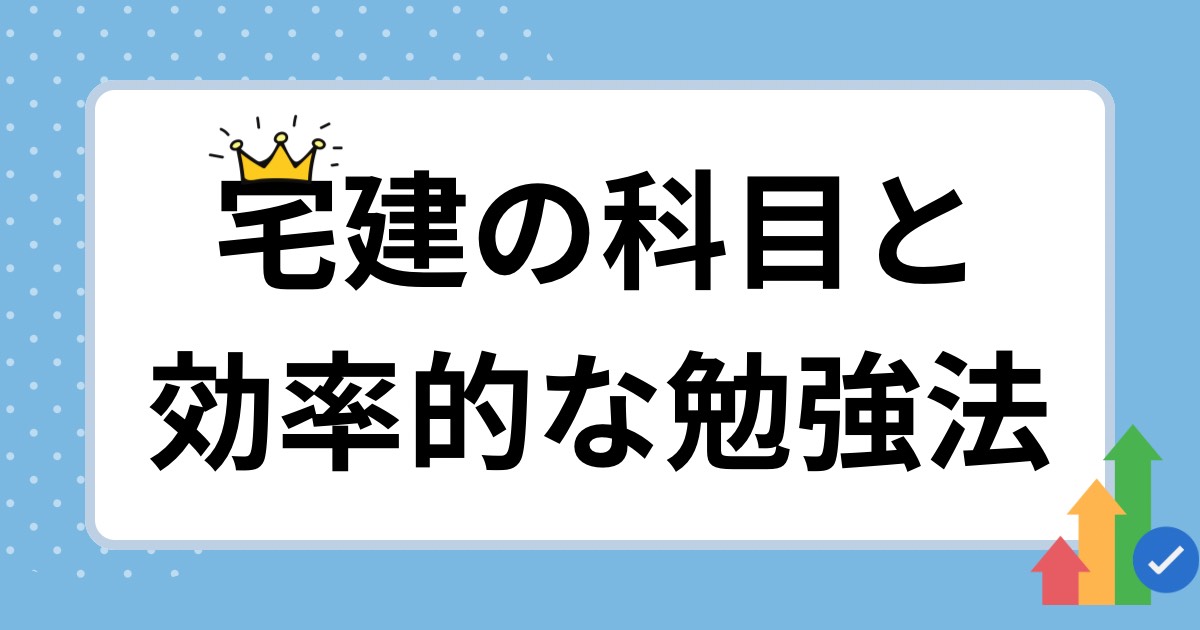









コメント