宅建は学校にいく必要がある?結論から言うとケース次第!
宅建は学校にいくひつようがあるのか?結論から言うと、あなたの性格と生活リズム次第です。
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
①独学でも合格は十分に可能
まず結論から言うと、宅建は独学でも十分に合格できます。実際、合格者の中には独学でコツコツ勉強して突破した人も多いです。
なぜ独学でもいけるのかというと、宅建の試験は「法律の基礎知識+過去問の理解」が中心だからです。つまり、範囲は広いけれど、出題傾向が明確で、繰り返し学べば知識が定着しやすいんですね。
たとえば、過去問集を中心に勉強して「出題パターンを理解する」ことを意識すれば、独学でも効率的に点数を取れるようになります。
ただし、独学で合格するには“自己管理力”が必要です。毎日コツコツ勉強を続ける習慣をつくれないと、途中で挫折するリスクも高くなります。
「勉強スケジュールを自分で組むのが苦手」「やる気が続かない」というタイプの人は、独学より学校の方が合っていますね。
②学校に通うべき人の特徴
学校に通うべき人は、ズバリ「時間管理が苦手な人」「一人だと続かない人」「質問できる環境が欲しい人」です。
学校に通うと、カリキュラムがしっかりしていて「今日はここを勉強する」というスケジュールを自動で管理してくれます。つまり、何をどの順番で勉強すればいいか迷わずに進められるんです。
また、講師にすぐ質問できるのも大きなメリット。宅建の法律用語や判例は、慣れるまで理解しづらいものも多いですが、講師に直接聞けばその場でスッキリ解決できます。
さらに、同じ目標を持つ仲間がいることでモチベーションも維持しやすくなります。「あの人も頑張ってるし、自分もやらなきゃ!」という気持ちが続くのは、通学ならではの良さですよね。
特に「何をどう勉強すればいいかわからない」「毎回やる気が波に左右される」という人には、学校通いはかなり効果的です。
③通う必要がない人の特徴
一方で、学校に通う必要がない人もいます。たとえば、「計画を立ててコツコツ進められる人」「集中力が高く自分を律せる人」「自宅学習環境が整っている人」です。
このタイプの人は、学校に通うことで逆にペースが乱れることもあります。講義のスケジュールに合わせる必要があるので、自分の得意分野を重点的に学ぶ時間が減ってしまうケースもあります。
また、宅建は市販の教材や通信講座でも十分にカバーできます。市販のテキストは非常にクオリティが高く、1冊2,000円前後で買えるのに内容は予備校レベルなんです。
自宅で集中できるタイプの人なら、むしろ独学や通信の方が費用も時間も効率的ですよ。
④判断に迷うときの考え方
「独学か学校か」で悩む人におすすめなのは、まず自分の“勉強スタイル”を知ることです。
具体的には、「今まで資格勉強をどんなふうに進めてきたか」を振り返ってみるのがいいですね。もし過去に「最初はやる気があったけど途中で挫折した」経験があるなら、学校のサポートが向いています。
逆に「自分で勉強計画を立てて成功したことがある」なら、独学でも十分戦えます。
どうしても判断がつかない場合は、まず無料の体験講義を受けてみるのもおすすめです。資格の大原やLECなどは、実際の授業を無料で視聴できる機会を設けています。
受けてみると、「自分には講義形式が合う」「思ったより自宅でも集中できそう」など、実感をもって判断できますよ。
宅建の学校に通うメリット5つ
宅建の学校に通うメリット5つについて解説します。
それでは、宅建の学校に通う具体的なメリットをひとつずつ見ていきましょう。
①学習スケジュールを自動で管理してくれる
宅建の学校に通う最大のメリットは、「勉強スケジュールを自動で管理してくれる」ことです。
独学だと、どの範囲をいつ勉強するのか、どの順番で進めるのが効率的なのかを自分で決めなければなりません。これが意外と大変で、計画を立てるだけで満足してしまう人も多いんですよね。
一方、学校では「この週は権利関係」「次は宅建業法」といった具合に、プロが最適な順番でカリキュラムを組んでくれます。つまり、余計なことを考えずに“勉強に集中できる”んです。
特に仕事や家事で忙しい人にとっては、「今日は何をやればいいか」が明確に決まっているだけで、かなり心の負担が軽くなります。毎回の授業で進捗を確認できるのも、モチベーション維持につながりますね。
「勉強の段取りを考えるのが苦手」「自分では続かない」という人にとっては、この管理サポートは本当に大きいです。
②質問や疑問をすぐに解決できる
宅建の勉強をしていると、「テキストのこの部分、何を言ってるの?」「この判例の意味がわからない」など、理解できない箇所が必ず出てきます。
独学の場合、ネットで調べても専門用語ばかりで余計に混乱することが多いんですよね。結局そのまま放置してしまって、理解が浅いまま次に進んでしまうケースもあります。
学校に通えば、わからないことをその場で講師に聞けます。プロの講師は例え話や図解を使って丁寧に教えてくれるので、理解のスピードがまったく違います。
また、授業後の質問タイムやメールサポートを活用できる学校も多く、疑問を「翌日までに解決できる」環境が整っているのも強みです。
理解できない部分を放置しないで済むことは、合格への近道です。勉強の効率も上がるので、時間の節約にもつながります。
③モチベーションを維持しやすい
独学で挫折してしまう人の多くは、「モチベーションが続かない」ことが原因です。宅建の勉強は数ヶ月単位の長期戦なので、最初のやる気だけでは乗り切れません。
学校に通うと、定期的に授業があり、自然と「勉強リズム」が生まれます。授業に行けば仲間がいて、講師の熱意にも刺激を受けるので、自然とやる気が戻ってくるんですよね。
「あの人も頑張ってるし、自分も負けてられない」という気持ちは、1人では生まれにくいものです。人とのつながりが勉強の継続に大きな力をくれます。
心理的にも、「自分は学校に通っている=やめづらい」という状況がプレッシャーになって、結果的に勉強を継続しやすくなります。
孤独になりがちな資格勉強の中で、「一緒に頑張る仲間がいる」ことは大きな支えになりますね。
④試験情報や出題傾向を早くキャッチできる
宅建試験は毎年少しずつ出題傾向が変わります。過去問を解くだけでは対応しきれない部分もあるんですよね。
学校では、最新の試験データや出題傾向をもとに「今年はここが狙われそう」といった情報をいち早く共有してくれます。
たとえば、ある年に「法改正が多く出題された」傾向があると、講師がそのポイントを重点的に解説してくれるんです。これが独学との差を大きく広げるポイントになります。
さらに、模試のフィードバックや講師陣の分析レポートを通じて、自分の弱点や改善点を客観的に把握できるのも魅力的です。
常に最新の情報を得ながら勉強できるのは、学校通いの強みですね。
⑤仲間と刺激し合える環境がある
最後に、学校のもうひとつの大きなメリットは「仲間の存在」です。
資格の勉強は孤独になりがちで、モチベーションが下がると一気にやる気を失うこともあります。しかし、学校に通うと同じ目標を持つ仲間がいます。
授業中の何気ない会話や、休み時間の「ここの問題難しくない?」なんてやり取りが、意外と大きな励みになるんですよね。
また、ライバルの存在も大事です。「あの人より点数を取りたい!」という気持ちは、いい意味でのプレッシャーになります。人とのつながりが努力を後押ししてくれるんです。
実際に、筆者自身も学校に通っていたときは、友人たちと模試の点数を競い合うことで勉強が楽しくなりました。孤独よりも「チーム感」が生まれるのが、学校通いの一番の魅力かもしれません。
宅建の学校に通うデメリット4つ
宅建の学校に通うデメリット4つについて解説します。
宅建の学校に通うとメリットもたくさんありますが、当然ながらデメリットもあります。
ここを正しく理解しておかないと、「思っていたのと違う…」と後悔することにもなりかねません。
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
①受講料が高くコスパが悪い場合も
まず一番多くの人が気にするのが「受講料の高さ」です。宅建の学校に通うと、平均して10万円〜20万円ほどの費用がかかります。
一見それほど高くないように感じるかもしれませんが、社会人にとっては決して安い金額ではありません。
しかも、講座の種類やオプションによっては、30万円近くになることもあります。
たとえば「通学+通信セット」「模試付き」「質問無制限プラン」などを選ぶと、想定以上に費用がかさむケースも少なくありません。
もちろん、「お金を払う=本気になれる」というメリットもありますが、正直に言うとコスパが悪い学校も存在します。
授業内容が古かったり、講師の説明が分かりにくい場合もあるんですよね。
筆者の知人にも、20万円の講座に通って「講義のテンポが遅すぎて自分には合わなかった」と後悔していた人がいました。
なので、支払う前に必ず「無料体験」や「資料請求」をして、講義の質や講師との相性を確かめておくのが大事です。
自分に合わない学校を選んでしまうと、時間もお金もムダになってしまいます。
せっかくのやる気を無駄にしないためにも、料金だけで決めず「サポート体制」や「講師の教え方」も重視しましょうね。
②通学時間がかかって効率が落ちる
通学型の学校は、当然ながら「通う時間」が発生します。
往復1時間、2時間かかることも珍しくありません。これが意外と大きな負担になります。
平日は仕事帰りに授業を受け、家に帰るのは夜10時過ぎ…。
翌朝また出勤となると、体力的にもかなりキツいです。
せっかく学校で学んでも、疲れがたまって復習の時間が取れない、なんてことにもなりかねません。
特に働きながら宅建を目指す社会人の場合、「通うこと自体がストレス」になるケースもあります。
学校に通うのが目的になってしまい、「授業を受けただけで満足」してしまう人も多いんですよね。
時間の使い方という点では、通信講座や独学の方が効率がいい場合もあります。
たとえば、通勤電車の中で動画講義を見たり、スキマ時間で過去問を解いたりと、柔軟に勉強時間を作れます。
「通学時間を勉強時間に変える」だけで、1日1〜2時間の差が生まれます。
宅建試験はとにかく継続が大切なので、時間効率をどう考えるかがポイントですね。
③自分のペースで進めづらい
学校ではカリキュラムが固定されているため、「自分のペースで進めたい人」には不向きな面もあります。
授業のスピードが合わなかったり、「もう少し復習したい」と思っても次の単元に進んでしまうことも多いです。
逆に、「もう知ってる内容なのに、何度も同じ説明をされて退屈」ということもあります。
自分の理解度に合わせて柔軟に進められない点は、学校のデメリットといえますね。
最近は録画講義やオンラインフォローが充実している学校も多いですが、それでもやはり「集団授業」という特性上、完全にマイペースというわけにはいきません。
また、「みんながいるから質問しづらい」「授業が進むのが早すぎてついていけない」という声もよく聞きます。
性格的に自分のペースでコツコツ学びたい人は、通信講座や独学の方が合っているかもしれません。
④合格保証があっても油断すると落ちる
最近は「合格保証付き」という宅建講座も増えています。
「合格しなければ全額返金」「来年の講義を無料で受けられる」など、一見すると安心できる制度ですよね。
ただし、ここには注意点があります。
合格保証があるからといって、「学校に通えば自動的に受かる」というわけではないんです。
実際のところ、合格保証には条件があります。 ・全授業出席 ・課題提出 ・模試の受験 などをすべてクリアしないと、保証が適用されないケースがほとんど。
つまり、“本気でやる人”しかその保証は意味を持たないということです。
学校に通うだけで満足してしまうと、当然合格は遠のきます。
学校のサポートを最大限活かすには、「自分から質問する」「授業後に復習する」など、主体的に動くことが大事です。
環境は整っていても、最終的に合格を決めるのは自分の努力なんですよね。
筆者の体験では、講義後に「今日の内容を自分の言葉でノートにまとめる」だけでも理解度が全然違いました。
学校はあくまで「勉強をサポートしてくれる場所」であって、「勉強を代わりにしてくれる場所」ではない、という意識を持つことが大切です。
宅建学校がおすすめな人・独学がおすすめな人
宅建学校がおすすめな人・独学がおすすめな人について、タイプ別に分かりやすく解説します。
「自分はどっち向きなんだろう?」と悩む方も多いですよね。
ここでは、あなたの性格・生活リズム・モチベーション傾向から、どちらが合っているのかを見極めるヒントをお伝えします。
①学校がおすすめな人の特徴
まず、宅建の学校に通うのがおすすめな人は、次のようなタイプです。
- 時間管理が苦手で、つい勉強を後回しにしてしまう人
- 「一人だとサボっちゃう」タイプの人
- 講師や仲間の存在があると頑張れる人
- 勉強リズムを決めてくれる環境がほしい人
学校の最大の魅力は「勉強しなくても強制的に勉強できる環境」があることです。
授業の日が決まっているから、「今日は疲れたからやめよう」と思っても、通えば自然と勉強することになります。
また、同じ目標を持つ仲間ができるのも大きいです。
宅建の勉強って、正直言うと孤独なんですよね。自分との戦いです。
でも、学校に通えば、周りも頑張ってるのが見える。「負けてられないな」と思えるのは、学校の強力な効果です。
さらに、講師の存在も大きいです。勉強がつまずいたとき、「こういう考え方をすると理解しやすいよ」と言ってもらえるだけで救われることもあります。
特に「スケジュール管理が苦手」「勉強法がわからない」「一人だと続かない」という人は、間違いなく学校の方が合っています。
筆者自身も過去に宅建を目指したとき、独学で何度も挫折しました。
でも、予備校に通い始めた途端に“勉強のリズム”ができて、あっという間に合格ラインを超えられたんです。
「環境に頼るのも立派な戦略」だと心から思います。
②独学がおすすめな人の特徴
一方で、独学が向いている人ももちろんいます。
- 計画を立ててコツコツ勉強できる人
- 自分で調べて理解するのが得意な人
- 費用をできるだけ抑えたい人
- 一人でも集中力を保てる人
宅建の試験は、毎年20万人以上が受験しますが、その中で独学合格者も多いです。
教材も優秀で、「みんなが欲しかった宅建士の教科書」「フォーサイト」「ユーキャン」などの通信教材を使えば、独学でも十分にカバーできます。
独学の最大の強みは、“自由さ”です。
勉強する時間も、進め方も、完全に自分次第。理解できない部分は立ち止まり、得意な分野はスピードアップできます。
ただし、注意点は「孤独に耐えられるかどうか」。
宅建は長期戦なので、やる気が落ちたときの“立て直し方”を持っておくといいです。
たとえば、「毎週の勉強時間を記録する」「SNSで進捗を発信する」など、モチベーションを維持する工夫が鍵になります。
もしあなたが「自分を律する力がある」「勉強する目的が明確」と感じているなら、独学でもまったく問題ありません。
③それぞれの勉強法のコツ
どちらのスタイルにも共通して言えるのは、「継続がすべて」ということです。
学校に通っても、独学でも、結局“毎日少しずつ積み上げられる人”が合格します。
学校に通う人は、「受け身にならないこと」が大事。授業を受けっぱなしにせず、必ず復習しましょう。
特に授業後の30分は記憶の定着率が高いので、「今日の内容をノートにまとめる」のがおすすめです。
独学の人は、「計画倒れにならないこと」がポイントです。
“完璧な計画”を立てようとせず、「1日30分だけ勉強する」といったミニ目標を積み重ねると続けやすくなります。
また、どちらの人も「過去問中心」で勉強するのが鉄則。
宅建は過去問の焼き直しが多いため、10年分を完璧にすれば、ほぼ合格圏内です。
④中間スタイル「通信講座」という選択肢
「学校に通う時間はないけど、独学は不安…」という人には、通信講座という中間スタイルがおすすめです。
最近の通信講座は本当に進化していて、動画講義・質問チャット・模試・AI学習サポートまで全部オンラインで完結できます。
代表的なのは「アガルート」「スタディング」「フォーサイト」などです。
特にアガルートは、宅建試験で圧倒的な合格率を誇ります。
理由は、“短時間で効率よく学べる構成”にこだわっているから。忙しい社会人でも無理なく進められるように作られているんです。
スタディングはスマホ完全対応で、通勤中や昼休みにちょこっと勉強できるのが魅力。
「机に座って勉強するのが苦手」という人にも合います。
通信講座は「学校の強制力」と「独学の自由さ」のいいとこ取り。
まさに、現代のライフスタイルに合った学び方です。
「通学する時間がない」「でも一人でやるのは不安」という人には、通信講座が最もバランスの良い選択ですね。
宅建学校の選び方とおすすめスクール
宅建学校の選び方とおすすめスクールについて詳しく紹介します。
宅建の学校って本当にたくさんありますよね。
「どこを選べばいいかわからない…」と悩む方も多いと思います。
ここでは、後悔しないための選び方と、実績のあるスクールを紹介します。
①宅建学校の選び方5つのポイント
学校選びで失敗しないためには、次の5つをチェックしましょう。
- 通学か通信かを最初に決める
- 講師の質を確認する
- サポート体制の充実度
- カリキュラムの更新頻度
- 無料体験・資料請求で相性を確かめる
まず大事なのは「通学か通信か」です。
通える時間がある人は、直接講師から学べる通学タイプが良いでしょう。
一方で、仕事や家庭の都合で通えない人は、通信講座一択です。
次に、講師の質。これは本当に大事です。
どんなにカリキュラムが良くても、講師の説明が分かりにくいと一気にモチベが下がります。
公式サイトの講師紹介や無料動画で「自分に合う話し方か」をチェックしておくと失敗しにくいです。
また、サポート体制も要チェック。
「質問対応はメールのみ」「返信まで3日かかる」なんて学校もあるので、質問しやすい環境かどうかを必ず確認しておきましょう。
カリキュラムについては、最新の法改正に対応しているかも大切です。
宅建試験は法改正が多いため、情報が古いと不利になることもあります。
最後に、無料体験は必ず受けましょう。
講義の雰囲気やスピード感、講師の話し方など、実際に受けてみないと分からない部分がたくさんあります。
体験して「この先生なら続けられそう!」と思えるかどうかが一番の判断基準です。
②資格の大原:対面サポートが強い王道スクール
資格の大原は、「対面でしっかり教わりたい」人にピッタリな学校です。
講義形式が明確で、初心者でも基礎から丁寧に学べます。
特に強いのが、質問対応と学習サポート。
講義後に講師へ直接質問できるだけでなく、復習フォローの教材も豊富なんです。
通学型の中では王道中の王道で、「まず失敗しないスクール」を選びたい人におすすめです。
| 特徴 | 対面サポートが手厚く、講師の質が高い |
|---|---|
| 受講スタイル | 通学・通信どちらも可能 |
| 料金目安 | 約180,000円 |
「通って勉強したい」「講師から直接アドバイスをもらいたい」という人には最も合う選択肢です。
③LEC東京リーガルマインド:分析力が光る老舗
LECは法律資格に強い老舗スクールです。宅建だけでなく、行政書士や司法書士でも有名ですよね。
そのノウハウを活かして、宅建でも出題傾向の分析力が抜群です。
特にLECの「短期合格カリキュラム」は、限られた時間の中で効率的に得点力を上げる構成になっています。
模試のクオリティも高く、本番の出題傾向にかなり近い内容で練習できます。
また、講師の説明が論理的で分かりやすいのもポイント。
「とにかく理屈で理解したい」「なぜこうなるのかを知りたい」というタイプの人に合います。
| 特徴 | 出題傾向の分析が的確。模試の完成度も高い |
|---|---|
| 受講スタイル | 通学・通信対応 |
| 料金目安 | 約160,000円 |
本格的に勉強したい人、理論派タイプの方にぴったりなスクールですね。
④アガルートアカデミー:通信でも圧倒的な合格率
通信講座の中でいま最も勢いがあるのが「アガルートアカデミー」です。
なんといっても合格率が高いことで有名。受講生の満足度も非常に高いんです。
アガルートの強みは、“無駄を省いた効率的な講義”。
必要な情報をコンパクトにまとめ、動画もテンポが良いので飽きずに続けられます。
また、質問対応が早く、オンラインでのサポートも手厚いです。
仕事や育児で忙しい人でも、スマホやタブレットでスキマ時間に勉強できるのが魅力ですね。
| 特徴 | 通信専門ながら合格率が高く、効率重視のカリキュラム |
|---|---|
| 受講スタイル | 通信のみ |
| 料金目安 | 約60,000円〜 |
「学校に行く時間はないけど、サポートが欲しい」という方には間違いなくアガルートがおすすめです。
また、最近はスマホ1台で完結できる「スタディング」も人気です。
移動中に動画を観て、夜は問題演習という“ながら勉強”ができるので、特に会社員にピッタリ。
結局のところ、「どの学校がいいか」よりも「自分が続けやすい環境」を選ぶのが大切なんですよね。
講義の内容よりも、“勉強を習慣にできる環境を作れるか”が合否を分けるポイントです。
まとめ|宅建の学校は時間管理が苦手な人におすすめ
宅建の学校は時間管理が苦手な人におすすめ、というテーマでまとめます。
| 項目 | 内容リンク |
|---|---|
| 学校がおすすめな人 | 学校がおすすめな人の特徴 |
| 独学がおすすめな人 | 独学がおすすめな人の特徴 |
| おすすめスクール | 資格の大原・LEC・アガルート |
| 学校のデメリット | 受講料の高さ・時間の制約 |
宅建の学校に通うべきかどうかは、結局のところ「あなたの性格とライフスタイル」で決まります。
独学でも十分に合格できる資格ではありますが、時間管理が苦手だったり、一人でモチベーションを保つのが難しい人には、学校という“勉強環境”が大きな支えになります。
学校に通えば、学習スケジュールを立ててもらえたり、質問がすぐできたりと、独学では得られない安心感があります。
また、同じ目標を持つ仲間ができることで、やる気を保ちやすいのも大きな魅力ですよね。
逆に、自分のペースで勉強したい人、費用を抑えたい人は独学で全然OKです。
通信講座という中間スタイルもあるので、「通うのは難しいけど一人は不安」という方にも選択肢はたくさんあります。
大切なのは、「自分が一番続けやすい環境を選ぶこと」。
どんなにいい教材を使っても、続けられなければ意味がありません。
宅建の勉強は、最初の3ヶ月が勝負。
この時期に“勉強を習慣化できるかどうか”が、合否を分けます。
そのためにも、学校や講座の力を上手に借りるのは立派な戦略なんです。
筆者がいちばん伝えたいのは、「宅建は努力が報われる資格」ということ。
正しい環境で、少しずつ積み上げれば、誰でも合格を掴めます。
もしあなたが今、「やる気はあるけど続かない…」「どう勉強すればいいかわからない」と感じているなら、ぜひ一度、学校や通信講座の無料体験を受けてみてください。
自分にピッタリな学び方が見つかるはずです。
一歩踏み出した瞬間から、合格への道はもう始まっています。
焦らず、あきらめず、自分に合った環境で、宅建合格をつかみ取りましょう!
最後に、学習の参考になる公式情報も貼っておきますね。
あなたのペースで、焦らず、宅建合格を目指してくださいね。応援しています!🔥




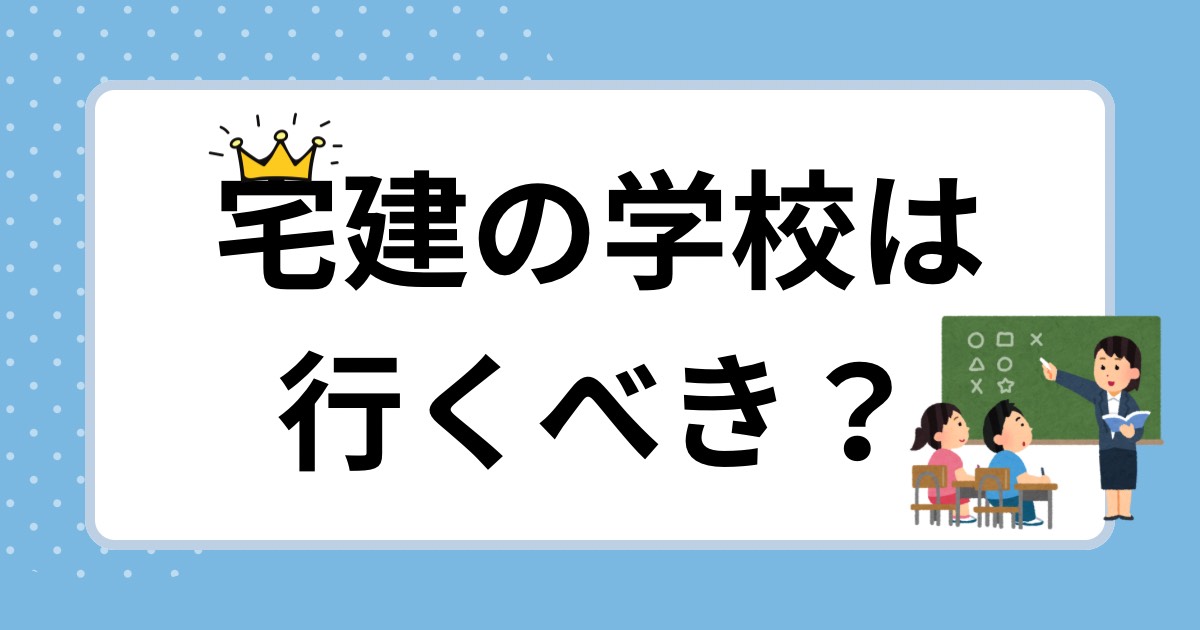









コメント