新人くん「宅建って、テキストなしでも受かるって本当ですか?」
タク「できなくはないけど、正直かなり厳しいね。」
「宅建 テキスト いらない」で検索している人の多くは、独学で合格を目指している社会人や、勉強時間を確保しづらい営業職の方たちです。
最近ではYouTubeや過去問アプリだけで合格したという声も増えていますが、実際のところ、それはごく一部の人に限られます。
私は現役の不動産営業マンとして働きながら、2回目の挑戦で宅建に合格しました。
同僚の中には「テキストをほとんど使わずにギリギリ合格」した人もいましたが、実務では知識不足でお客様に不安を与えたり、上司から指摘を受けたりしていました。
この記事では、宅建テキストが本当にいらない人の特徴、逆に必要な人の条件、そしてテキストを使わずに学ぶ場合の現実的な方法まで、現場目線でリアルに解説します。
「宅建テキストはいらない説」に振り回される前に、自分に合った勉強スタイルを見極めてほしい。そんな思いで書いています。
この記事を読めば、「テキストを使うべきか」「他の教材で十分か」が明確になり、ムダなく最短ルートで合格を目指せるようになります。
宅建テキストはいらない?
それでは、具体的に見ていきましょう。
①不動産経験者ならテキストなしでも合格可能
不動産の実務経験がある方であれば、テキストを使わずに合格できる可能性があります。
日々の仕事で契約書や法令上の制限、宅建業法などに触れているため、出題のイメージを掴みやすいからです。
実際、私の周りでも営業マンで独学合格した人は何人かいます。テキストよりも過去問演習や問題集の繰り返しに集中して、知識を実戦形式で定着させたパターンですね。
ただ、これは“現場経験が豊富”な人に限られます。日常的に法令や契約内容を見ていない人にとっては、そもそも問題文の意味が分からないという壁にぶつかります。
「なんとなく雰囲気で解ける」レベルでは、合格ラインの35点を超えるのは難しいです。ですので、経験者でもテキストを完全に手放すのはリスクがあります。
最低限、要点整理や分野ごとの復習のために、1冊だけでもテキストを持っておくのがおすすめです。
②法律知識がある人は理解がスムーズ
法律関係の知識がある人、例えば行政書士やFP、司法書士などを学んだことのある方であれば、テキストがなくてもある程度理解は進むでしょう。
法律の読み方に慣れているため、問題集の解説を読んでも違和感なく理解できます。
ただし、これは“前提知識がある人”に限られます。一般的な社会人がゼロから学ぶ場合、宅建業法や法令上の制限の言い回しにかなり苦戦します。
私個人としては、やはりテキストを使って体系的に学ぶことを強くおすすめします。
というのも、私の同僚で「テキストをほとんど使わずに」YouTubeと過去問、模試、アプリだけで勉強して合格した人がいました。36点でギリギリ合格(令和3年度・合格点34点)でしたが、5点免除がなければ正直危なかったレベルです。
しかもその後、実務で宅建を使う場面で「法令上の制限」や「権利関係」でわからないことが多く、お客様に不安を与えてしまったり、上司から『ほんとに宅建受かったんよね?』と言われたりしていました。
事業用物件の案内時に「建築基準法」や「都市計画法」に関する説明が求められたときも、テキストで学んでいなかった内容が多く、現場で答えられないことが何度もあったそうです。
この経験を見て、私は改めて「合格と実務は別物」だと痛感しました。試験では選択肢の正誤を見抜くスキルが求められますが、現場では条文や制度を“説明できるレベル”の理解が必要です。
だからこそ、テキストを使って体系的に学ぶことは、回り道のようで実は一番の近道なんです。
新人くん「やっぱりテキストって、大事なんですね…」
タク「そうだね。効率だけで見ると遠回りに見えるけど、理解の深さでは全然違うんだよ。」
宅建テキストが必要になるケース
宅建テキストが必要になるケースについて解説します。
それでは、それぞれのケースを見ていきましょう。
①未経験で法律用語が初めての人
不動産業界の未経験者で、法律に触れたことがない人は、テキストが必須です。
なぜなら、宅建試験では「権利関係」や「法令上の制限」といった法律分野が全体の半分近くを占めており、専門用語の理解ができないと、そもそも問題文を読む段階でつまずいてしまうからです。
たとえば「地上権」や「抵当権」などの言葉が日常生活に出てくることはありませんよね。
こうした基礎用語を一から説明してくれるのがテキストの役割なんです。
新人くん「法律って、言葉の意味が難しいですよね…」
タク「そうだね。宅建の問題文は、一語の理解で正答率が大きく変わるんだよ。」
テキストは単なる参考書ではなく、“言葉の地図”みたいなものです。 問題演習を始める前に、用語の意味をテキストでしっかり整理しておくことが合格の第一歩になります。
②学習時間が限られている社会人
働きながら勉強している社会人にとって、時間は最大の課題です。
だからこそ、限られた時間で最短ルートを進むために、テキストを使って「重要なポイントだけを押さえる」ことが大切です。
YouTubeやアプリも有効ですが、情報が分散してしまいがちで、効率を欠くリスクがあります。
テキストを1冊決めて、それを「基準」として使うだけで、勉強の迷いがなくなります。
新人くん「テキストを軸にして、足りない部分を動画とかで補う感じですか?」
タク「まさにそれ。テキストがあるだけで、情報が“整理された状態”で頭に入るんだよ。」
社会人学習者こそ、迷わない勉強法を選ぶことが大事なんです。
③基礎知識を体系的に押さえたい人
「宅建の仕組みをちゃんと理解したい」「点だけでなく線で知識をつなげたい」という人にも、テキストは必須です。
テキストは過去問と違って、章ごとに「全体の関係性」が整理されています。
権利関係の中で“借地借家法”と“区分所有法”がどう違うのか、宅建業法の“重要事項説明”と“37条書面”がどう関連しているのか、 この「つながり」を理解するのが、得点アップのカギになります。
私自身も1年目は過去問ばかり解いていましたが、途中で「そもそも何の話をしてるのか」が分からなくなり、結局テキストに戻りました。
そこから点数が一気に伸びた経験があります。
やみくもに問題を解くよりも、テキストで体系を押さえる。 遠回りに見えて、最短で合格するルートなんですよ。
新人くん「なるほど…テキストって、“点をつなげるための地図”みたいな感じなんですね!」
タク「その通り。地図なしでゴールを目指すのは、やっぱり難しいんだよ。」
宅建テキストの代わりに使える教材5選
宅建テキストの代わりに使える教材について紹介します。
「テキストを買うのは避けたいけど、勉強方法を確立したい」という人に向けて、実際に代用できる教材を紹介していきます。
①過去問集・問題集
テキストの代わりに最も実用的なのが「過去問集」です。
宅建試験では、過去問の焼き直しや類似問題が多く出題されるため、過去問を軸に学習を進めることで、出題傾向を自然とつかむことができます。
ただし、解説が簡略的なものもあるため、理解が追いつかない部分は要注意です。
個人的には、アガルートやLECの「肢別過去問集」など、解説がしっかりしているタイプを選ぶのがおすすめです。
新人くん「過去問を繰り返すだけでも効果ありますか?」
タク「うん。3周以上やると、問題のパターンが体に染みついてくるよ。」
②YouTube講義(ゆーき大学など)
無料でわかりやすく学べるのが、YouTube講義です。
中でも人気なのが「ゆーき大学」。 実際に私も受験期に何度も見ました。
短時間でポイントを押さえられる上に、図解や例え話で理解しやすいのが特徴です。
ただ、動画はあくまで“補助教材”。 動画だけで理解したつもりになると、記憶の定着が弱くなります。
気になるテーマを動画で確認 → ノートに要点をまとめる、という流れで使うと効果的です。
③通信講座の無料体験版
最近では、多くの通信講座が無料体験やお試し動画を提供しています。
アガルートやスタディング、ユーキャンなどは、宅建業法の一部講義を無料で視聴でき、教材のクオリティを確認できます。
特にスタディングはスマホ完結型なので、スキマ時間に動画を見て、学習アプリで復習する流れが非常に便利です。
教材の構成や説明の流れが整理されているので、「体系的な理解が苦手」という人には特におすすめです。
新人くん「通信講座って高いイメージでしたけど、体験版だけでも使えるんですね!」
タク「そうそう。無料範囲でもかなり使えるから、活用しない手はないよ。」
④解説が詳しい有料問題集
市販の問題集の中には、テキスト並みに解説が充実しているものもあります。
特に「宅建士合格のトリセツ」シリーズや「みんなが欲しかった宅建士の問題集」は、1問ごとにイラスト付きで構造が整理されています。
テキストを買わずに済ませたい人でも、このタイプの問題集なら、ほぼ同等の学習効果を得ることができます。
ただし、図や解説を読む力がないと、内容が“暗記の羅列”になってしまうこともあります。
そのため、章末の「まとめページ」も併せて活用しながら、論点ごとに整理していくのがポイントです。
⑤模試・予想問題集
最後に紹介するのが「模試」や「予想問題集」です。
これは直前期に特に効果的で、時間配分の練習にもなります。
模試はLECやTACの全国公開模試のような有料版でも良いですが、YouTubeで無料公開している模試も増えています。
模試を通じて「自分の弱点がどの分野にあるか」を知ることで、最終的な得点アップに直結します。
新人くん「模試って、やってみると全然違うんですね…」
タク「うん。時間内で解く感覚をつかむのは、本番で大きな武器になるんだ。」
こうした教材を組み合わせれば、テキストがなくてもある程度の学習は可能です。
ただ、効率よく理解を深めるためには、やはり“自分の学び方に合った教材”を選ぶことが大切です。
宅建合格を目指す人へのおすすめ勉強法
宅建合格を目指す人へのおすすめ勉強法について、立場や環境ごとに紹介します。
自分の状況に合わせて学習スタイルを選ぶことで、宅建合格への最短ルートが見えてきます。
①不動産経験者=過去問特化で効率重視
不動産業界で働いている方は、過去問特化型の勉強法がおすすめです。
実務を通じて宅建業法や契約内容に触れているため、基礎知識はある程度備わっています。
そのため、過去問を中心に「出題パターンの把握」と「問題の癖」を分析しながら学ぶことで、短期間で得点を伸ばせます。
具体的には、1日1分野ずつ解くリズムを作ると良いです。
間違えた問題は印をつけて、3周目で完璧に仕上げましょう。
新人くん「過去問だけでいける人って、やっぱり実務経験者なんですね。」
タク「そう。実務で触れてる分、問題文の意味をイメージしやすいんだ。」
②未経験者=通信講座で体系的に学ぶ
未経験者や法律に不慣れな人は、通信講座が最も効率的です。
通信講座は「必要な知識を順序立てて学べる」ように設計されており、独学のように迷う時間がありません。
アガルートやスタディングのように、動画+スマホ学習+問題演習を一体化した講座は特におすすめです。
一度ペースが掴めると、1日30分でも積み上がっていくのが実感できます。
新人くん「通信講座って高いけど、時短になるならアリですね。」
タク「そう。金額よりも“迷わない時間”のほうが価値があるよ。」
未経験者が最初に時間をかけてでも体系を理解しておくと、後の独学にも必ず役立ちます。
③コスト重視派=無料教材と動画を組み合わせる
「できるだけお金をかけたくない」という人は、無料教材と動画を組み合わせて学ぶのが現実的です。
スタディングの無料体験動画や、YouTubeの講義を使えば、主要科目の基礎部分は十分に理解できます。
その上で、過去問アプリや市販の安価な問題集を併用すると、効率よく全体をカバーできます。
ただし、無料教材は情報が古かったり、法改正に追いついていない場合もあります。
法改正情報は国交省のサイトで確認するなど、自分で最新情報を取りに行く意識が必要です。
新人くん「無料だけでも結構できそうですね!」
タク「うん。でも“無料=自己管理が必要”ってことも覚えておいてね。」
④独学チャレンジ派=問題演習+法改正情報を追う
独学で挑戦する場合は、「自分で学習設計を作る」意識が大事です。
まず、過去問と予想問題を中心に回しながら、分からない部分はテキストやネットで調べる。
そして、年度ごとの法改正をチェックして「去年の知識が通用しない部分」を更新することが重要です。
具体的には、国土交通省の公式発表や不動産系YouTubeチャンネルを定期的に確認しておくと安心です。
私自身も独学2回目で合格したときは、この“情報更新”が鍵でした。
前年と同じ教材を使っているだけでは、点数が伸びないんです。
新人くん「宅建って、法律の試験だから情報が古いと危ないんですね…」
タク「その通り。だから、独学でも“常に最新”を意識して勉強するのがポイントだよ。」
どんな勉強法を選ぶにしても、「理解→演習→更新」というサイクルを回すことが、最終的な合格への最短ルートです。
まとめ|宅建テキストはいらないは本当?現場から見た結論
| 項目 | 内容リンク |
|---|---|
| 不動産経験者 | 過去問特化で効率重視 |
| 未経験者 | 通信講座で体系的に学ぶ |
| コスト重視派 | 無料教材と動画を組み合わせる |
| 独学チャレンジ派 | 問題演習+法改正情報を追う |
「宅建テキストはいらない」という言葉には、たしかに一理あります。
不動産経験者や法律知識のある人なら、過去問やYouTube講義を活用して合格することも現実的です。
しかし、テキストを完全に手放すと、理解が断片的になったり、法改正への対応が遅れたりするリスクがあります。
実際、私の同僚もテキストを使わずに合格しましたが、実務で「知らない知識」が多く苦労していました。
合格することだけを目的にするならギリギリでも通用しますが、「宅建士として信頼される力」を身につけたいなら、テキストで基礎を固めることが大切です。
新人くん「たしかに、合格だけじゃなくて“その先”も考えた方がいいですね。」
タク「そう。資格はゴールじゃなくて、スタートなんだよ。」
結論として、「テキストはいらない」と断言するのは危険です。
経験や目的に応じて、“テキストを使うべき人”“使わなくてもいい人”を見極めることが、賢い選択です。
もし自分がどちらに当てはまるかわからない場合は、まず通信講座の無料体験を使ってみてください。
体系的に学ぶ価値を感じられれば、自然と「テキストを使う理由」も納得できるはずです。
出典:スタディGO「テキストを使わずに宅建合格はできる?」/最終確認日:2025年10月




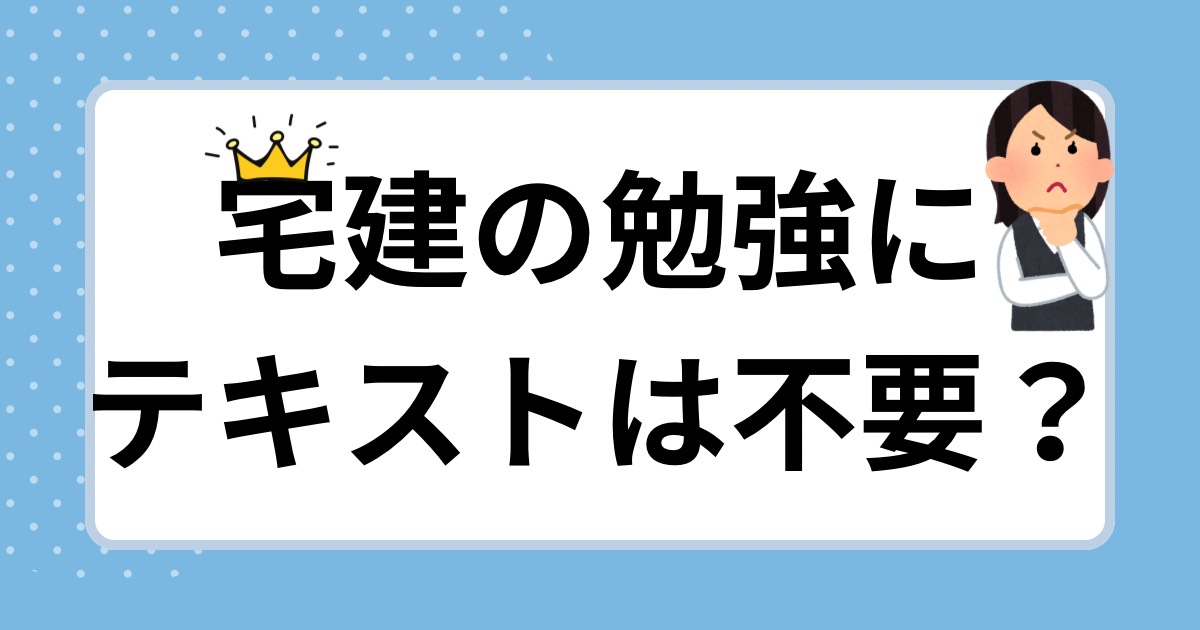









コメント